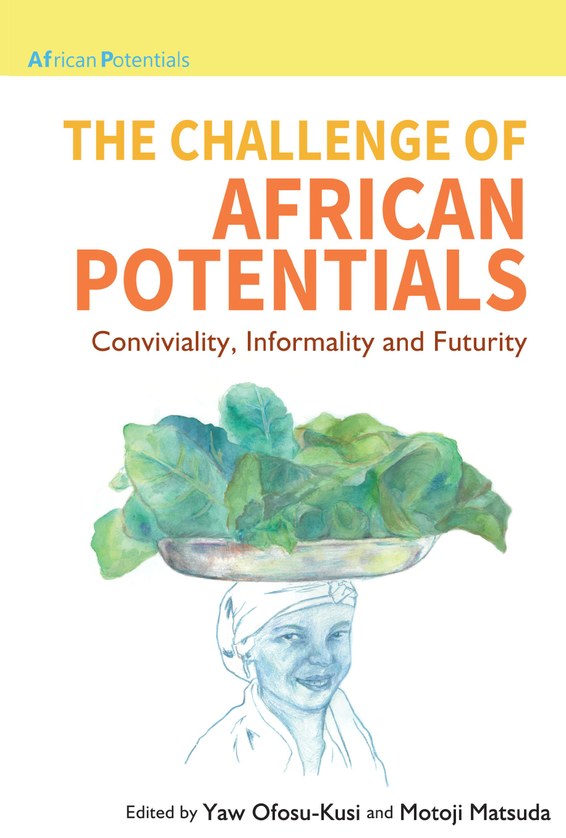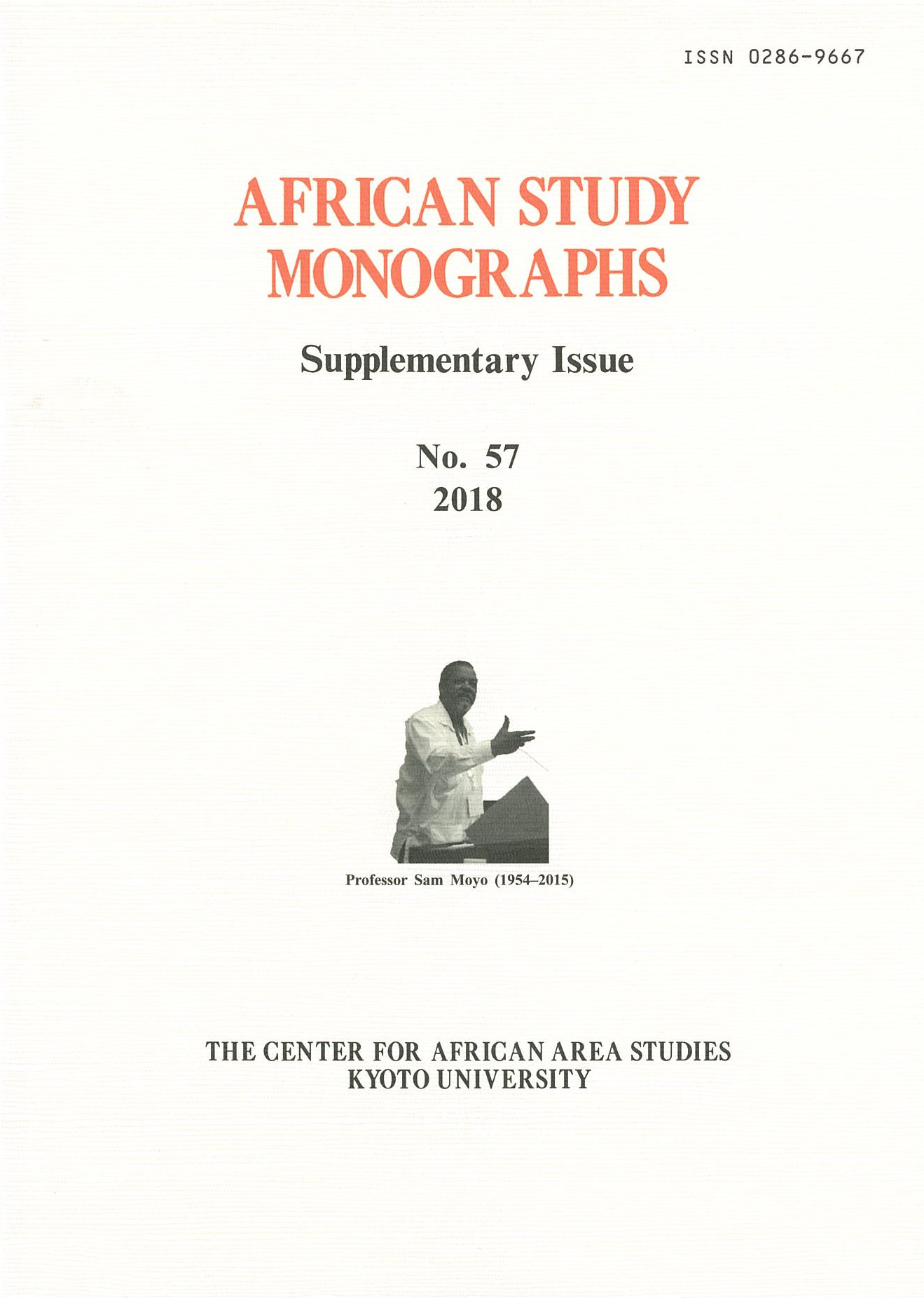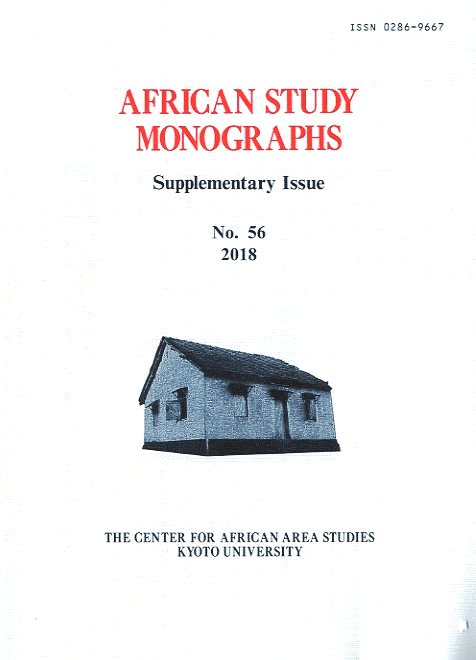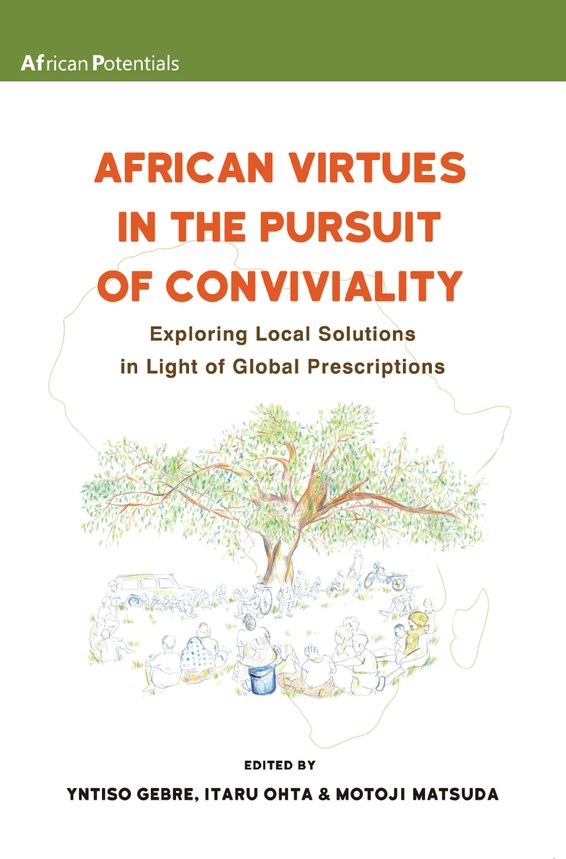「うなづき症候群と生きる村」
西 真如
(派遣先国:ウガンダ/海外出張期間:2016年12月31日〜2017年1月7日)
今夜も野焼きをするけど、一緒に来ないか――そう声をかけてくれたお父さんについて小屋を出た。暗い畑地を通りぬけてゆく道すがら、夜のほうが風が吹かないので火を入れるには都合が良いのだと説明してくれる。10分ほども歩いただろうか、今日はここからあの奥の方まで焼くのだと言って藪に火をつけた。燃え広がろうとする火を、一緒に来た助手の若者が木の枝で叩いて鎮圧しつつ、帯状に焼いていく手際の良さに驚かせられる(写真1)。この村の人たちは、こうして毎年、同じように火入れを繰り返してきたのだろう。そんなことを思いながら野焼きの作業を見ていると、この地域でおこなわれた凄惨な暴力が収束してから、まだ10年も経たないということが、信じ難く思われる。

写真1:野焼きの火
ここで「お父さん」と呼ぶのは、ウガンダ北部のアチワ川流域での調査でお世話になった世帯のあるじである。ウガンダ北部では1980年代から、「神の抵抗軍」を名のる反乱軍とウガンダ政府軍とが衝突する中で、虐殺や誘拐、略奪が横行した。暴力がおおむね収束し、アチョリの人々が暮らす村に日常生活が戻り始めたのは2007年以降のことであるが、ちょうどその頃からアチワ川流域では、「うなづき症候群」(Nodding Syndrome) と呼ばれる病気の流行がみられるようになった。患者の多くは10 代までに発症し、頻繁なてんかん症状を呈することに加えて、何らかの知的障害を伴うことが多い。疾患そのものは直ちに命を奪うものではないが、水浴びの最中に意識を失って溺死したり、意識のないまま徘徊して行方不明になる患者もいる。てんかん発作への偏見から通学を拒まれたり、知的障害のために教育機会を失う子どもも少なくない。近くの町には国営の診療所があり、抗てんかん薬を無償で受け取ることができるが、薬の種類も職員の知識も限られており、治療を受けても発作が収まらない患者が多い(写真2)。

写真2:現地で用いられる抗てんかん治療薬のパッケージ
私はこれまで、エチオピアでHIV感染症に関する医療人類学調査に従事してきたが(西 2017)、最近になって、うなづき症候群の調査を目的にウガンダ北部を訪れるようになった。村で私の相手をしてくれるお父さんも、身内に患者を抱えている。患者の治療に加えて問題なのは、患者を抱えた家族の負担である (Sakai 2015)。患者の危難を未然に防ぎ、生活の質を確保するには日常的な見守りが欠かせないが、患者の家族はそれぞれ、生計のための労働に従事したり、学校に通う時間が必要である。患者の祖母が健在である場合、日常的な世話役を期待されるが、彼女らにもじぶんの人生がある。医療資源が限られたアフリカの農村で、どのように患者とその家族の生活の質を確保するのかを考えることが、私の調査の課題の一つである。
参考文献
Finnström, Sverker. 2008. Living with Bad Surroundings: War, History, and Everyday Moments in Northern Uganda. Duke University Press.
西真如2017「公衆衛生の知識と治療のシチズンシップ――HIV流行下のエチオピア社会を生きる」『文化人類学』81 (4): 651–69.
Sakai, Kikuko. 2015. Patients Who Face Many Difficulties: A Case Study of a Community Based Organization for the Care and Treatment of Nodding Syndrome in Northern Uganda. Presentation at the Minpaku Project Meeting “How Do Biomedicines Shape Life, Sociality and Landscape in Africa?” National Museum of Ethnology, Suita, Japan, September 25–27, 2015.