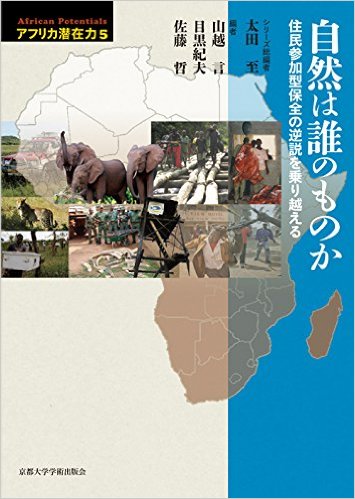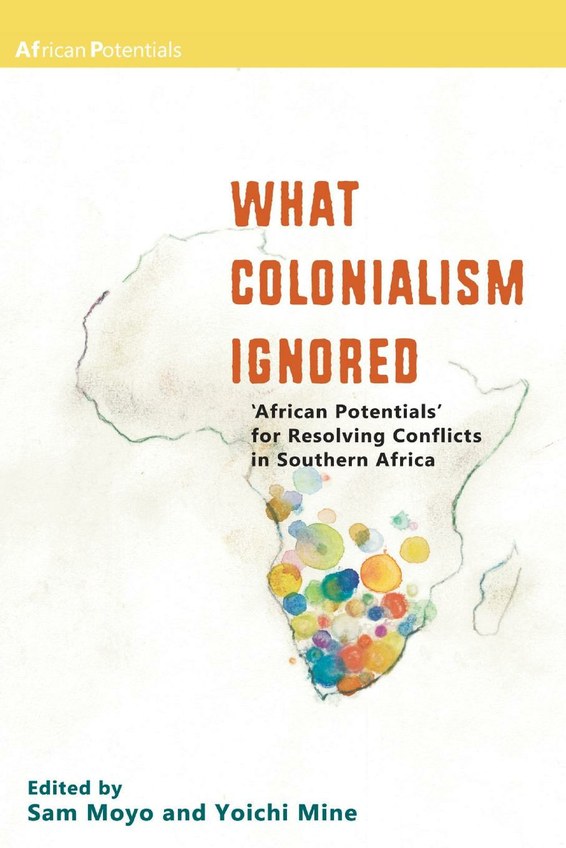| (派遣国:タンザニア、派遣期間2011年8月~9月) |
|---|
| 「焼畑移動耕作にみられる共同性の再編」 原子 壮太(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・研究員) |
| キーワード:クランの土地, 共同性, 焼畑移動耕作 |
研究目的今回、タンザニア南部高地の山麓に位置する農耕民ベナの村に派遣された。私は、この山村の基幹生業である焼畑移動耕作にかんする調査を2006年より継続している。耕作地は、村の周辺に分布し、そこではいくつかの世帯が隣り合って小集落を形成している。この小集団は、ムゴーウェ(mgowe)、チャマ(chama)といった労働交換、協働による焼畑の火入れ作業、種籾の交換など様々な互助活動の基本的な単位となっている。しかし、そのメンバーシップは固定的なものではなく、焼畑の移動のたびにこの小集団は解散し、他所で再編成されることがわかっている。本研究は、この小集落の形成のされかたがどのように変容してきたのか、社会的環境の変動を踏まえつつ論じることを目的としている。 調査から得られた知見と今後の展開聞き取り調査によると、この小集落の原型は、いくつかの父系親族集団からなるまとまりであったという。長年にわたって特定の親族集団が居住し耕作し続けた土地には、地名が付され、それはやがて緩やかな境界をもったクランの土地として認知されるようになっていった。 しかし、1974年に集村化政策が実施されたことにより、すべての世帯は集住村に家屋を建設する事が求められ、共同農場における労務を課された。また、集住村には医療、初等教育、公社による農産物の買い取りなど、村人を惹きつける行政サービスもあった。こうして集住村の求心力が増してくると、遠方の耕作地は次第に耕作されなくなってゆき、集住村に比較的近い土地が開墾されるようになったのである。 こうした変化のなか、集住村から遠く離れた土地を耕作していた世帯は、集住村での地縁関係をたよりに様々なクランの土地を移動しながら耕作するようになっていった。一方、クランの土地を保有する世帯の多くは、このような世帯の移入に対して寛容であった。その結果、親族関係に必ずしもよらない地縁関係からなる集団が集住村の周辺に集落を形成するようになっていったのである。焼畑耕作地における小集団の再編という現象は、このような移入世帯が他のクランの土地を渡り歩く事によって生じているのである。 2006年頃より、換金作物であるインゲンマメの乾期作が、焼畑耕作地の合間の谷底湿地で行われるようになり、次第に盛んになっていった。この新しい農法は、連作が可能であり、イネの裏作としておこなえることから、導入する世帯が増えつつある。しかし、この定着的な農耕は、移入世帯の連作を地主世帯が認めず争いに発展するなど、移入世帯と地主世帯との間に確執を生む場合もあるようだ。今後、移入世帯と地主世帯との間でどのような交渉がなされるのか注視してゆきたい。  写真1 焼畑耕作地での互助労働(チャマ)  写真2 谷底湿地でのインゲン豆の乾期作 |