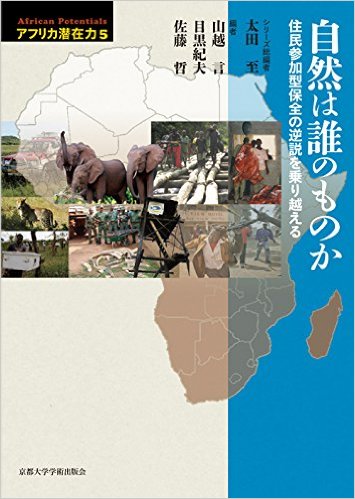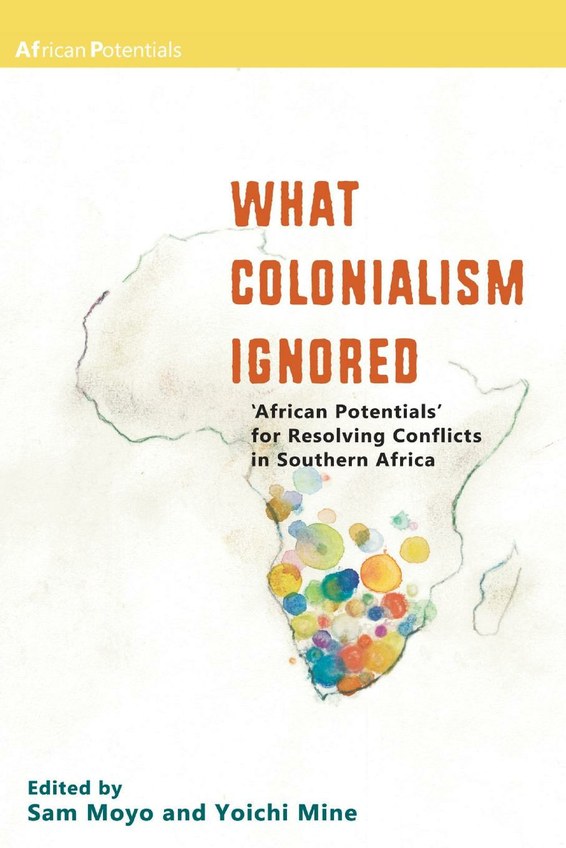| (派遣先国:ケニア/派遣期間:2015年7月〜8月) |
|---|
| 「家族として共に生きる:マウマウ戦争後の男と女の葛藤」 松岡陽子(山口大学) |
| キーワード:マウマウ戦争, マウマウ, 植民地政府, 反植民地主義, 勾留キャンプ, 新村 |
研究の背景と目的 1950年代、ケニアでは土地の奪還と独立を求めるキクユ人によって結成された秘密結社マウマウがイギリス植民地政府に対して蜂起し、およそ10年にわたる期間、闘争が繰り広げられた。ケニアは1963年に独立したが、その後もマウマウについた人々と植民地政府についた人々の間で互いに敵対し、分裂の傷跡は埋まらなかったと言われている。 また、戦争の経験はおよそ男女別で異なり、若い男性はマウマウの仲間として捕えられ、勾留キャンプや刑務所に収容され、非常に厳しい生活をそこで強いられた。一方、女性や子どもなど戦闘員になりえない人々は植民地政府よりマウマウの「被害者」として扱われ、「新村」と呼ばれる急ごしらえの要塞化したムラに収容された。そこでの生活も厳しいものだったが、男性の収容先よりはまだましな環境であった。 終戦後、男女は再び出会い、一つの家族として再スタートをきったが、異なる戦争体験、相反する戦争に対する意識をもつなかで、どのように家族や親族の絆を深めていったのか明らかにすることを目的とした。 得られた知見 マウマウ戦争にかんする資料はほとんどがキクユと植民地政府の対立に焦点があてられているが、エンブも全民族がマウマウ戦争に巻き込まれた経緯をもつ。エンブがキクユの状況と異なるのは、白人に占拠された土地がないこと、マウマウ運動が盛んになって日が浅かったことなどがあげられる。それ以前は、植民地政府支配下でもエンブ独自の生活を続けることができ、政府に不満もなく暮らしていた。1950年前後より、植民地政府と対立を深めるなかで、戦力や支持者を求めるマウマウの脅しともいえる勧誘によってエンブの多くがマウマウの加入者にさせられたが、彼らの胸中は複雑だった。実際は彼らのほとんどはマウマウにも植民地政府にも、そのどちらにも身を委ねるつもりはなかった。彼らは脅迫的になるマウマウと植民地政府の間に挟まれ、生きるために状況に応じてしぶしぶマウマウ側になったり、植民地政府側になったりしていた。 そのようなエンブ人の戦後の絆の紡ぎ方として見えてきたのは、異なる経験をしてきた男女が家族として生活を共にするとき、あいまいなものをあいまいなままにして暮らしていたことがわかった。男性も女性も、表向きマウマウ側についた者も、表向き植民地政府側についた者も、彼らは状況に応じて立場を変え、語る視点を変えて、互いに語り合ってきたのである。当時、植民地政府の手足となって動いた民兵たちも、マウマウの宣誓を受けた経験をもつ者がほとんどで、彼らもまたその場その場に応じて、植民地政府側の立場から、もしくはマウマウ側の立場から語る。つまり、エンブには明確な「マウマウ側」と「植民地政府側」などなかったのである。 これはエンブだけの固有の状況なのか、それともほかの地域にも言えることなのかは、別途検証が必要であるだろう。  本調査で得られた知見は調査における反省的なものである。世論、国際政治経済、論者の背景、そして語り手の背景次第で、「真実」はいかようにも表現される。「真実」は時代や状況次第で変わるものであり、玉虫色をしている。歴史を振り返る時、私たちはそのことを前提としておかなければならない。 現在、反植民地主義のイデオロギーは大きなインパクトをもって私たちの言論を支配している。それゆえ、その議論に沿う語りを語り手から取り出そうとすると、エンブにおいてもいくらでも引き出すことができる。しかし、そこに捨象される多くの事実や現象が隠されていることにも調査者は配慮しなければならない。研究者の研究テーマに期待する欲望を排し、可能な限り現地の厚い記述をすることの重要性を改めて問いたい。 |