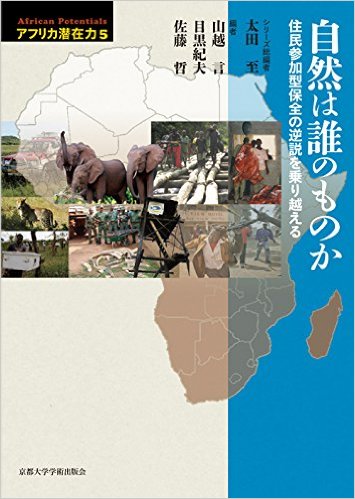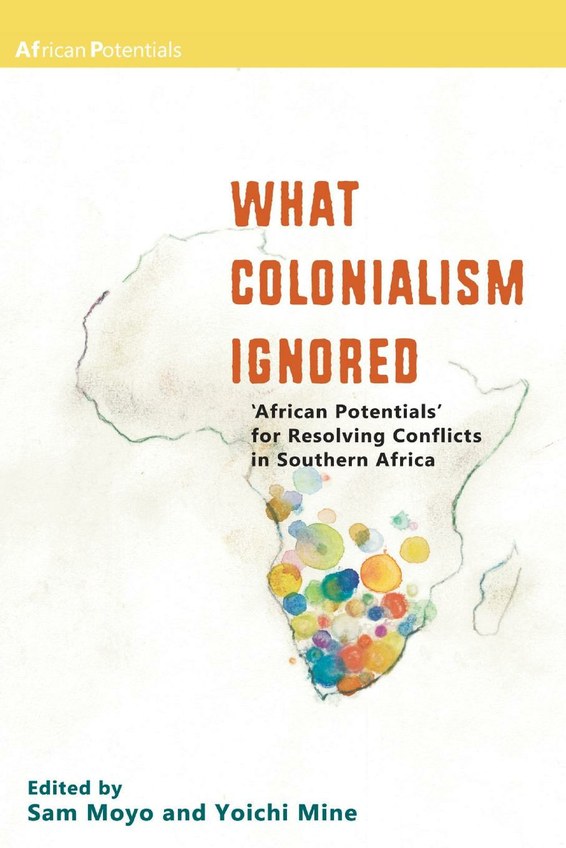| (派遣先国:ウガンダ/派遣期間:2015年8月) |
|---|
| 「ウガンダの紛争後地域における『うなづき症候群』の問題に対処する 住民組織に関する研究」 坂井紀公子(京都大学 アフリカ地域研究資料センター) |
| キーワード:ウガンダ北部, 紛争後地域, 「うなづき症候群」, ALCONS, 社会的なケア |
研究の背景と目的本研究は、ウガンダ北部に暮らす人びとが、いかなる方法で長期紛争後の社会にもたらされた諸問題に対処しているのか、その一端を明らかにすることである。 ウガンダ北部は、政府軍と反政府軍の間で20年以上続いた紛争地帯にあり、地元民の大半は同地域内に設置された国内避難民キャンプに強制収容され、食糧不足と不衛生な環境下で長期滞在を余儀なくされた経験をもつ。また、主たる反政府勢力であった「神の抵抗軍」(Load’s Resistance Army:LRA)の戦闘員の8割が同地域で拉致された子どもで構成されていたため、長期にわたる紛争によって、多数の子どもが兵士となった。政府軍と反政府軍との間で和平合意が締結され停戦状態となった2006年から、住民は避難民キャンプ地を出て故郷へ帰還しはじめたが、その前後から子ども達のあいだで原因不明の奇病「うなづき症候群」(Nodding Syndrome:以下、NS)の発症者が増加した。症状は、「うなづく」「眠るように意識がなくなったり、突然に倒れたり」などのてんかん様発作とともに心身の発達遅滞である。キャンプ生活を経験した子たちの発症が多いことから、劣悪なキャンプ生活が子どもの脳の成長過程に悪影響を及ぼしていた可能性が指摘されている。米国疾病研究所(CDC)や世界保険機構(WHO)が大規模な疫学調査を実施したが、いまだに原因も根本治療の方法も不明である(WHO 2013)。現在、この紛争後地域は、NSの治療やケアにかかわる問題のほかに、避難民キャンプからの引き揚げにともなって発生している土地所有の問題や、元子ども兵士の社会復帰の問題など、解決困難な諸問題を抱えている。 ウガンダ国内外において、現在NSに対する治療方法の確立をめざした疫学調査が実施されているが、医学的調査への偏りが指摘されている(van Bemmel et al. 2014)。長期のケアを必要とする小児患者ケアの実態把握と、患者家族とそのコミュニティへの支援が急務となっており、これらの問題に焦点をあてる社会調査の重要性が増している。医療インフラが貧弱な地域におけるヘルスケアの供給を扱った研究では、生物医学上では理想的なケアが、対象社会の実情をまったく顧慮しない場合、それは、強引な介入行動と化し、かえって地域医療システムの発展を阻害する危険性があることが指摘されている(波佐間 2015)。復興途上の地域において、支援とともに家族やコミュニティによる患者ケアのニーズと実態、その問題点を明らかし、その可能性も提示することが重要であろう。以上の問題意識を背景に、この研究では、紛争後の社会において、NS患者の社会的なケアの在り方を検討する。 得られた知見ウガンダ北部におけるNS患者数は約3000人で 、国の公式発表では2012年以降、新たな発症者はいない。発症者が集中する地域は、キトゥグム県、ラムォ県、パデー県、グル県で、いずれもアチョリ・ランドと呼ばれるアチョリ民族が暮らす地域にあたる。調査地は、グル県のパイチョ準郡・カル-アリ行政教区・A村である。2014年から村内で患者のケアに関する予備調査を実施しており、以下の点を確認した。
不十分な医療体制と奇病が珍しくない状況下で、村民はNS患者と患者をもつ家族(以下、患者世帯)に対してどのような態度を示しているのであろうか。川口(2014)は、隣接したパデー県の状況について、差別的な言動がある反面、罹患者の増加により地域社会では同情的な見方もでてきていて、排除と包摂が同時にみられる状況を報告している。今回の調査では、患者の日常生活を記録する過程で、患者世帯の屋敷外において下記の場面に何度も遭遇した。
いずれもNS患者と直接の親族関係にはない人びとの対応事例である。表立った差別的な行為が見られなかったと同時に、間接的に患者を見守る状況が多く見受けられた。社会全体で、排除よりも見守るという土壌がいっそう醸成されている可能性がある。 A村では、患者世帯が中心となって結成したALCONS(Alliance for Communities with Nodding Syndrome)という住民組織が活動している。2013年にNS患者と患者世帯の支援と研究を目的としたネットワーク(以下、「NS対策ネットワーク」)が日本人の有志によって結成され、その働きかけによって、同じ年にALCONSも設立された(佐藤 2014)。結成当時、NS発症者を有する県・地域で、患者の支援を主目的とした住民組織はALSONのみであった(Kato 2014)。2015年時点のメンバー数は32人で、そのうちの23人が計31人の患者を有する。活動目的は、①NS患者のケア状況と栄養状態の改善、②患者世帯の所得向上、③NS患者とともにコミュニティが健康的に暮らせる生活環境の改善、④原因解明や治療方法の確立にむけた専門家との研究協力である。現在、①と②の目的達成を目指して、畑の共同耕作と役牛・乳牛の共同飼養を行うとともに、①と③への取り組みとして、不定期ではあるが、「NS対策ネットワーク」の支援により、患者への薬の配布や、心身に障害を持つ患者が多いことから、現地の専門家がボランティアによる特殊教育に関する学習会も実施している。さらに④の活動として、報告者の研究に協力している。本報告書では、共同耕作と乳牛飼養の活動を取り上げる。 共同耕作地は一年間のみ利用する条件でメンバーが持ち回りでALCONSに無償提供しており、毎年2~3エーカーに主食のキャッサバや副食に欠かせないラッカセイやゴマを栽培している。収穫物はメンバー内で分配し、患者の食料補充と栄養状態の改善に役立てているが、収穫量が少ないため、販売までには至っていない。したがって、患者世帯の所得向上という目標へは道半ばの状態にあり、耕作地の更なる拡大が必要とされている。  写真1 共同耕作の様子 この課題を克服するために、2014年に「NS対策ネットワーク」から牛耕用のウシ2頭と犂が寄贈されたが、彼らは一度も牛耕に成功していない。ウシを管理していたALCONSの議長は、反抗するウシの態度について、「初めに無理に広い範囲を耕作させてからというもの、まったく命令を聞かなくなった」と説明している。また、ALCONSの書記は、毎日メンバーが交替でウシたちを放牧させることになっているが、当番を忘れるメンバーが多いために、放牧が十分ではない日もよくあると述べ、彼らがウシの扱い方に慣れていない様子や適当な放牧をしていた様子がうかがえた。ウシは働く気配がなく、現在もメンバーが手で耕作し、耕作地の拡大は困難な状態である。 ALCONSは、2015年3月に「NS対策ネットワーク」からの支援を得て2頭の乳牛も購入し、乳牛飼養を開始した。患者の栄養状態の改善が目的である。役牛とともに乳牛もまた、メンバーが交替制で放牧することになっていたが、上記のような扱い方であったため、1頭は具合が悪くなり、死ぬ前に屠っていた。そして、一部の肉をメンバーへ無料で分配し、残りを村民に販売し、組織の活動費に充てていた。その後、残った1頭もやせ細っていき、子供を出産するどころではなく、患者へのミルク配給という活動目標はいまだに達成されていない。  写真2 委託後のウシ放牧の様子 両活動に共通する問題点は、ウシの共同管理の難しさにある。まず、メンバー間のウシの管理技術にはかなりの差があると考えられる。かつては紛争地域であったこの地域では、多くの家畜が略奪されていた。また、ほとんどの村民がキャンプ暮らしを経験した人たちである。長期のあいだウシの群れを放牧させることはほぼ不可能であったと推測される。ALCONS内にウシの扱いに長けた経験者が少なく、しかも個人間の経験や知識の差が大きかったことは十分に考えられる。 つぎに、ウシを放牧させる負担がメンバー間で均等ではなかったことが考えられる。通常アチョリの社会では、放牧は子供から青年男性の仕事として行われることが多く、女性が行うことはあまりない。女性メンバーが当番の日は、その世帯の男性や子どもが代わりにウシを放牧させていた。ALCONSの書記への聞き取りから、女性たちは放牧をさせる代役を探すことに面倒さを感じており、交替制の放牧への関わりが積極的ではなかったことが明らかになった。メンバー構成をみると、32人中17人が女性メンバーで、全体の半数以上を占めていた。さらに、問題は性別役割分業の慣例だけではない。ウシの放牧は患者世帯が感じていた心配をより強める可能性があった。患者世帯は世帯内の労働力不足に悩んでいる。患者の労働力だけではなく、患者を見守る者の労働力まで当てにできないからである。労働力不足は、耕作面積や収穫量のみならず収入の伸び悩みをも意味する。そして、子どもたちに十分な教育を受けさせることが困難になり、患者世帯は、将来には世帯間に大きな経済格差ができるのではないかと危惧していた(佐藤 2014)。ALCONSの3分の1の世帯は女性が世帯主である。これらの世帯にとって労働力不足に由来する心配事はより深刻であった可能性が高く、世帯内の貴重な労働力を奪いかねないという点で、交替制の放牧は女性メンバーの負担の大きい活動といえる。 以上の理由により、ウシの管理がうまくいかなかったり、放牧が適当になっていたりしていた可能性がある。乳牛1頭が亡くなったのちに、多数のメンバーが、乳牛も役牛も売り払い、そのお金で放牧の必要がないヤギを購入し、メンバーに分配することを希望していた。ヤギの個人飼養を希望した多くが女性メンバーであった。 ②の一時的な達成には寄与するが、結果的には①と②の達成が遠のくであろうヤギ分配計画の代わりとして、2015年の年末に別の計画が進められた。メンバー全員がお金を出しあい、ウシの管理が得意なALCONSのメンバーに3頭のウシの管理を委託した。また、「対策ネットワーク」からの支援金を利用して2頭の役牛を訓練師に預け、耕作できるよう躾つけた。その結果、2016年1月に乳牛が仔牛を出産し、ようやくミルクをだしはじめた。2頭の役牛も働くようになり、3月からの耕作に利用される予定である。 今回の報告では、共同耕作とウシの共同飼養における問題点を指摘するのみにとどまったが、患者のケアという点からこれらの活動を考えると、コミュニティにおける患者ケアの可能性が指摘できる。ALCONSは、隔週の土曜日に共同耕作を実施しており、活動終了後には1時間程度のミーティングも行っていた。緊急の議題がある場合にも不定期に集まっている。こうやって頻繁に集まり、よく食事を作ってともに食べ、時にはメンバー同士で患者を預かったりもしていた。情報を交換し相談する事で、互いの患者の症状や対処方法もわかるため、預ける/預かる関係が成立しやすいと考えられる。また、耕作時やミーティングにはNS患者も一緒に集まることが多いのだが、患者同士もよく顔を合わせることで仲よくなり、それ以外の日にも患者たちが一緒に遊んだり互いの家を行き来したりする光景がよく見られた。共同耕作や共同飼養は多くの問題をもたらすが、患者をもつ者たちが物理的にともに時を過ごす機会も提供しており、親族関係を越えた患者の社会的なケアの場を育む可能性をもっている。  写真3 ALCONSミーティングの様子(いつも女性の参加率のほうが高い) 冒頭では、紛争後地域においてNSの問題のほかに、土地所有の問題や元子ども兵士の社会復帰の問題といった諸問題が山積していると言及したが、ALSONSの活動地域においても、これらの問題が活動に影響を与え始めている。ALCONSには複数のクランメンバーが集まっており、クラン間で土地の所有をめぐる争いが、メンバー間の関係性に変化を与えている状況を確認した。今後の課題は、ALCONSの他の活動の分析とともに、これらの問題が社会的なケアを考えるうえでどのような作用を及ぼすのかを注視していくことである。 参考文献:
|