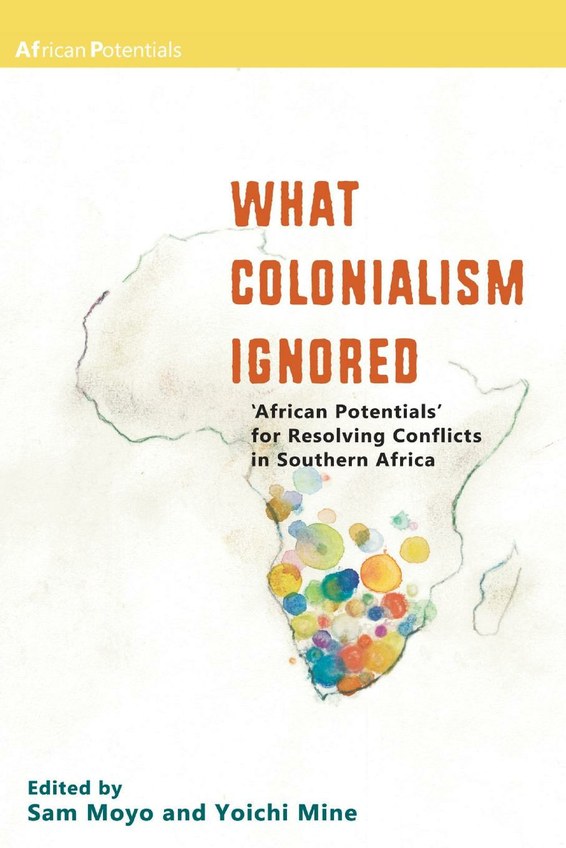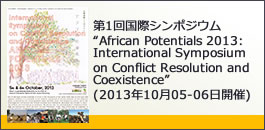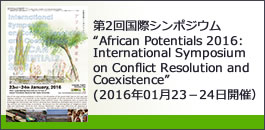[社会・文化ユニット第6回研究会/第7回公開ワークショップ]Petr Skalník「Chiefdom in Africa: An Institution of the Past or for the Future?」(第7回Kyoto University African Studies Seminar (KUASS) との共催、2012年10月09日開催)
日 時:2012年10月9日(火)15:00 – 17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階小会議室1
プログラム
15:00〜16:30
Petr Skalník (University of Hradec Kralove, Czech Republic)
ピーター・スカルニック(フラデツ・クラーロヴェー大学、チェコ共和国)
“Chiefdom in Africa: An institution of the past or for the future?”
「アフリカの首長国―過去の遺物的な制度か、それとも未来に活用できるのか―」
16:30〜17:30
質疑応答
要旨
Chiefdoms have been in many ways transformed during the colonial and post-colonial times but they still exist in many parts of Africa, Oceania, the Americas and even in Asia. In Europe and non-native America various institutions such as political parties, trade unions, sports clubs and corporations function in ways that resemble chiefdoms. Chieftaincy in Africa is partly discredited and partly revered as a moral authority. In Ghana people and ethnic groups, especially those labeled “acephalous” vie for attaining chiefly status. “Chieftaincy quarrels” lead to armed clashes, unrest and loss of identity. At the same time the modern state in Africa is mostly corrupt, structurally weak or violent towards its own citizens. Chiefs still enjoy high moral status or strive to regain it. At the moment one witnesses revival of chiefdoms’ role as central institution of African society. The solution to the dilemmatic situation might be to “tame” the imported state by according to the chiefs the role of watchdog of democracy. I call it the New Indirect Rule, based on equality of state and chiefdom principles. Is it a wishful thinking or a viable project? What can we learn from Africa?
アフリカ、オセアニア、アメリカ、そしてアジアなど、多くの地域に存在する首長国は、植民地時代から各国の独立後の期間に、さまざまな側面で変化してきたが、いまでも存在している。ヨーロッパ社会と(移民による)アメリカ社会では、政党や労働組合、スポーツクラブ、さまざまな法人といった多様な組織が、こうした首長国と同じような機能を担ってきた。アフリカにおいては、首長の名誉や評判は一部では失墜したが、他方では道徳的な権威として尊敬されている。ガーナでは現在、とくに「無頭的(acephalous:首長をもたない)」と形容される民族集団が、首長の地位を確立しようとして張り合っており、武装闘争もひきおこされ、アイデンティティの喪失や社会的不安をもたらしている。同時にまた、アフリカにおける近代国家は、どこでも汚職が横行し、構造的に弱く、そして市民に対して暴力的である。それに対して首長たちは、より高い道徳的地位を維持しているし、また、そうした地位を獲得しようと努めている。すなわち、現在のアフリカでは首長国が、重要な組織・制度として再生・復興しているのである。このような近代国家と首長国のあいだのジレンマに満ちた関係は、どのように解決されるのだろうか。ひとつは、首長たちに民主主義の番人(監視人)としての役割を与えて、外来の制度である近代国家を「馴化する」ことであろう。このことをわたしは、近代国家と首長国の原理の共通性にもとづく「新しい間接統治(New Indirect Rule)」と呼ぶことにする。これは現実性のない希望的観測だろうか、それとも実現と成功が見込める企てだろうか。そしてわたしたちは、アフリカから何を学ぶことができるだろうか。
[第7回公開ワークショップ/社会・文化ユニット第6回研究会]Petr Skalník「Chiefdom in Africa: An Institution of the Past or for the Future?」(第7回Kyoto University African Studies Seminar (KUASS) との共催、2012年10月09日開催)
日 時:2012年10月9日(火)15:00 – 17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階小会議室1
プログラム
15:00〜16:30
Petr Skalník (University of Hradec Kralove, Czech Republic)
ピーター・スカルニック(フラデツ・クラーロヴェー大学、チェコ共和国)
“Chiefdom in Africa: An institution of the past or for the future?”
「アフリカの首長国―過去の遺物的な制度か、それとも未来に活用できるのか―」
16:30〜17:30
質疑応答
要旨
Chiefdoms have been in many ways transformed during the colonial and post-colonial times but they still exist in many parts of Africa, Oceania, the Americas and even in Asia. In Europe and non-native America various institutions such as political parties, trade unions, sports clubs and corporations function in ways that resemble chiefdoms. Chieftaincy in Africa is partly discredited and partly revered as a moral authority. In Ghana people and ethnic groups, especially those labeled “acephalous” vie for attaining chiefly status. “Chieftaincy quarrels” lead to armed clashes, unrest and loss of identity. At the same time the modern state in Africa is mostly corrupt, structurally weak or violent towards its own citizens. Chiefs still enjoy high moral status or strive to regain it. At the moment one witnesses revival of chiefdoms’ role as central institution of African society. The solution to the dilemmatic situation might be to “tame” the imported state by according to the chiefs the role of watchdog of democracy. I call it the New Indirect Rule, based on equality of state and chiefdom principles. Is it a wishful thinking or a viable project? What can we learn from Africa?
アフリカ、オセアニア、アメリカ、そしてアジアなど、多くの地域に存在する首長国は、植民地時代から各国の独立後の期間に、さまざまな側面で変化してきたが、いまでも存在している。ヨーロッパ社会と(移民による)アメリカ社会では、政党や労働組合、スポーツクラブ、さまざまな法人といった多様な組織が、こうした首長国と同じような機能を担ってきた。アフリカにおいては、首長の名誉や評判は一部では失墜したが、他方では道徳的な権威として尊敬されている。ガーナでは現在、とくに「無頭的(acephalous:首長をもたない)」と形容される民族集団が、首長の地位を確立しようとして張り合っており、武装闘争もひきおこされ、アイデンティティの喪失や社会的不安をもたらしている。同時にまた、アフリカにおける近代国家は、どこでも汚職が横行し、構造的に弱く、そして市民に対して暴力的である。それに対して首長たちは、より高い道徳的地位を維持しているし、また、そうした地位を獲得しようと努めている。すなわち、現在のアフリカでは首長国が、重要な組織・制度として再生・復興しているのである。このような近代国家と首長国のあいだのジレンマに満ちた関係は、どのように解決されるのだろうか。ひとつは、首長たちに民主主義の番人(監視人)としての役割を与えて、外来の制度である近代国家を「馴化する」ことであろう。このことをわたしは、近代国家と首長国の原理の共通性にもとづく「新しい間接統治(New Indirect Rule)」と呼ぶことにする。これは現実性のない希望的観測だろうか、それとも実現と成功が見込める企てだろうか。そしてわたしたちは、アフリカから何を学ぶことができるだろうか。
[南部アフリカ・クラスター第3回研究会]村尾るみこ「『共生』を再考する―ザンビア西部州における農地利用に注目して」(2012年7月20日開催)
日 時: 2012年7月20日(金) 17:00~19:00
場 所: 東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム1
プログラム
「共生」を再考する―ザンビア西部州における農地利用に注目して
村尾るみこ(東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所)
報告
ザンビア西部州では植民地時代、バロツェ協定によるロジ王国の自治が認められてきたが、1964年のザンビア独立時に政府によって協定が一方的に破棄された。西部州では自治の獲得に対して根強い運動が継続されており、2011年の大統領選挙で勝利したサタ新大統領の公約もあって、ロジ王国を中心とする独立運動が本格化している。アンゴラの内戦によってザンビア西部州へ移住してきたンブンダという民族の人びとが、民主化、経済成長、新土地法の政策のもとで、どのように農地利用をしているのかを議論した。人々は1940年代以降にアンゴラより移住し、ロジ王国の慣習地においてキャッサバ栽培を中心とする焼畑農耕を営んでいる。1970年代に、移住はピークに達した。移住民はザンベジ川の氾濫原では耕作することは許されず、アップランドの貧栄養なカラハリサンドにおける耕作活動のみが許されている。移住民はリンボと呼ばれる居住集団を構成し、3~4世代の親族または婚姻、知人・友人関係が結ばれている。リンボの長は農耕儀礼や土地の分配について重要な裁量をもつ。焼畑に隣接する森林については、焼畑をすでに開墾している者が、開墾の権利をもつ。現行の移住民の焼畑農耕は広大な面積を必要とし、自然林の減少とともに、やがて立ちいかなくなる危険性が高く、生計経済を多角化する動きがある。リンボや村など社会組織のあり方、流動性のきわめて高い社会集団における土地の交渉について、議論がなされた。(大山修一)
[政治・国際関係ユニット第5回研究会]秋林こずえ「紛争・平和研究とジェンダー研究―先行研究レビュー」(2012年07月20日開催)
日 時:2012年7月20日 15:00~17:00
場 所:東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム1
プログラム
「紛争・平和研究とジェンダー研究―先行研究レビュー」
秋林こずえ(立命館大学)
報告
まず秋林氏は、ジェンダーと紛争・平和をめぐる議論や実践活動が、国連を中心とした国際社会で歴史的にどのように展開してきたのかをまとめた。とくに、2000年の安保理決議1325「女性・平和・安全保障」は、平和・安全保障政策へのジェンダー視点の導入や武力紛争下で女性を保護する必要性への言及がなされた点で重要である。つぎに、この安保理決議1325に関連して展開してきたジェンダーと紛争・平和研究を、トピックごとにまとめてレビューした。「1325決議の分析、批判」については、決議の採択過程をめぐる分析や決議の内容の限界をめぐる議論、「国連と女性、ジェンダー」では、平和の文化を女性の地位向上にどう貢献させることができるのかをめぐる議論、「軍事基地・長期軍隊駐留と女性、ジェンダー」では、基地とホストコミュニティの関係をめぐる研究や基地周辺にくらす女性自身による報告、「軍事主義とジェンダー」ではC.Enloeらによる女性を利用した軍事化がなされる過程や戦場と銃後の連続性を検討した研究、「PKOとジェンダー暴力」は平和活動部隊の駐留にともなう人身売買やレイプの発生をめぐる研究、「平和構築とジェンダー」では女性が平和構築過程に果たす役割をめぐる議論、「移行期、ポスト・コンフリクトのジェンダー正義」では、移行期正義におけるジェンダー正義の遅れを指摘した研究、「マスキュリニティと平和」では加害主体として男性が社会化される過程を分析した研究、「紛争における女性の役割、平和構築における女性の役割」では、平和だけではなく戦争に女性が果たす役割を包括的に捉えた研究、がそれぞれ取り上げられた。
質疑の時間では、1325決議が具体的に現実社会での紛争や平和構築にいかなる影響を与えたのか、伝統的な女性の役割は平和構築過程でどのように取り扱われているのか、国際社会の場でアフリカ女性が積極的に活動する姿とアフリカ農村部の「家父長制」下における周縁化された女性の姿をいかに連続的なものとして考えることができるのか、といった議論がなされた(佐川徹)
[西アフリカ・クラスター第3回研究会]大山修一「ニジェールの人口増加問題と『現金獲得の糸口』―農耕民社会からみた牧畜民とのコンフリクトの背景―」(2012年07月14日開催)
日 時:2012年7月14日(土)15:00~17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階 301室
プログラム
「ニジェールの人口増加問題と『現金獲得の糸口』―農耕民社会からみた牧畜民とのコンフリクトの背景―」
大山修一(京都大学)
報告
ニジェールの人口増加率は3.5%と非常に高く、合計特殊出生数は7.1、20年で人口が2倍になる驚異的なペースである。どうして人口が急増するのか、ハウサの農村社会の論理を”harkuki(動き)”という概念で説明したうえで、農耕、牧畜、副職業、出稼ぎといった積多角的な経済活動に積極的に従事する人々の姿を示した。農村では、外部社会からの現金収入の多寡に応じて経済格差が大きく、所有する畑の面積、収穫量、家畜飼養のサイズに大きな差異が存在する。急増する人口によって、相続で受け取る畑の面積も縮小する傾向が強い。農耕や牧畜といった村内活動では自給ができない世帯も増加している。そうした世帯では、食料不足が慢性化しており、雨季における牧畜民による作物の食害で賠償金を得ようする人々も出現している。農耕民は、収穫したトウジンビエを故意に畑のなかに放置しておき、家畜がトウジンビエを食べたことをもって、牧畜民から賠償金を得ようとするのである。ハウサ社会では、このようなことを、「現金獲得の糸口(Bidan kudi)」と呼ぶこともある。サヘル地域では、雨季における農耕民と牧畜民の衝突が頻発し、その理由として稀少な土地資源をめぐってコンフリクトが起きると説明される。しかし、実際には、土地をめぐって争うのではなく、作物の食害をめぐる事実の認定をめぐって、意見が衝突し、その交渉がまとまらないときに、武力衝突に発展することが多い。食害認定の交渉では、当事者だけではなく、農耕民、牧畜民ともに代理人をたて、その代理人どうしは顔見知りであることが重要である。サヘル社会における、農耕民と牧畜社会のあいだで起きるコンフリクト、および、その修復に対する人々の取り組みを議論した。(大山修一)
[東アフリカ・クラスター第2回研究会]山本佳奈「季節湿地の利用をめぐる住民の対立と和解―タンザニア・ボジ高原の事例―」(2012年07月14日開催)
日 時:2012年7月14日(土)15:00~17:30
場 所:稲盛記念館3階 小会議室1
プログラム
「季節湿地の利用をめぐる住民の対立と和解-タンザニア・ボジ高原の事例-」
山本佳奈(日本学術振興会特別研究員/京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)
報告
報告では、1986年の構造調整計画の導入以降、タンザニア南部のボジ高原においてコーヒー園への転換にともなうトウモロコシ畑の狭小化が顕著になったことが述べられ、それが引き金となって起こった季節湿地の耕地化をめぐる住民の対立と和解のプロセスについて、2つの異なる事例が紹介された。ある村の事例では、土地不足の若者を中心とする耕地化の推進派と、湿地に残る神聖な森や放牧地を守ろうとする長老・村評議会・村民会議とが対立したが、推進派が独走して耕地開発をすすめた後に、1つの森と湿地(放牧地)の一部を残して耕地化することで両者が和解した。別の事例では、ある程度、湿地の耕地化が進んだ後に、村評議会が残された湿地(放牧地)の耕地分譲を決めたが、これに反対する放牧者・村民会議が、上位の行政アクター(県)に働きかけて、放牧地を確保した。
討論では、村の最高議決機関である村民会議や、1999年村落土地法で村の土地の配分主体となっている村評議会が機能しつつ、それらの決定があまりにも簡単に反故にされることが議論された。とりわけ、1つ目の事例において、村民会議で湿地の耕地化を認めなかった保守多数派が、決定を無視した湿地開発を黙認し、やがて保守派の長老も含めて次々と追従していったことに関心が集まった。
ケニアやルワンダでは同様のルール違反者がでた場合、必ずといってよいほど暴力的な制裁が加えられたり、県レベルの警察力介入や法的係争に発展したりすることが紹介され、タンザニアではいまだ人口あたりの「開発可能な土地」が比較的多く残ることによって、土地をめぐる紛争が激化しない可能性が指摘された。
また、村民会議は、いったんは長老や村評議会など伝統や権威に従う「総意」を出しつつ、社会的・経済的な状況の変化にそぐわない場合はその評決の反故を黙認したり、あるいは村評議会の暴走を諌めるために上位レベルの行政に働きかけるなど、巧妙に紛争を回避しつつ変化を合理的に制御しているようにも見えること、こうした特徴は、村民に加えて県から派遣された地方行政官が有力なメンバーとなっているという特異なメンバー構成に因るかもしれないことなどの検討課題が提起され、今後、他のアフリカ諸国の村行政組織との比較などを通じて議論を深めていく必要性が確認された。(近藤史)
[第1回アフリカの紛争と共生セミナー]「2011年度海外派遣者報告会」(2012年07月14日開催)
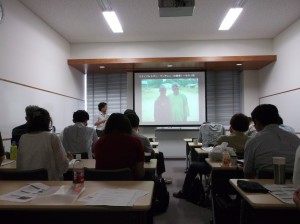
日 時:2012年7月14日(土) 11:15〜14:45
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階小会議室
プログラム
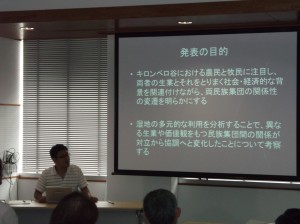
11:15-11:45
大野哲也(桐蔭横浜大学)
葛藤する二つの正義―ケニア・カカメガの森の保存に反対する運動から―
11:45-12:15
岡野英之(日本学術振興会特別研究員/大阪大学大学院国際公共政策研究科)
いかに武力紛争は波及するか―シエラレオネ・リベリア紛争にみる武装勢力の同盟網―
12:15-12:45 休憩

12:45-13:15
加藤太(信州大学農学部食料生産科学科・JSPS特別研究員)
氾濫原をめぐる農民と牧民の対立の回避と協調関係の発展
―タンザニア・キロンベロ谷の事例―
13:15-13:45
中沢美保子(神戸大学大学院国際協力研究科博士課程)
タンザニアにおける遺児の生活状況と教育への影響
13:45-14:15
原子壮太(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科研究員)
焼畑耕作における出作り集落の離合集散と森林資源の共有
-タンザニア南東部の山村の事例-
14:15-14:45
山本めゆ(京都大学大学院文学研究科博士課程)
ポスト・アパルトヘイトの南アフリカにおける人種分類の再編成
―華人コミュニティ100年間の経験に注目して―
要旨
葛藤する二つの正義
―ケニア・カカメガの森の保存に反対する運動から―
大野哲也(桐蔭横浜大学)
世界の多くの地域では、小さなコミュニティをいかに活性化させるのかという問題に苦慮している。そのような状況において、それらのコミュニティにある独自の自然や文化を国立保護区にして地域活性化を目指すということが試みられている。政府が自然や文化を国立保護区に指定して、それを観光資源化するのである。
国立保護区には、それ以外にも大きな意味があった。国立保護区の「保護しながら発展を目指す」という理念は、それまで多くの国で維持されてきた「開発か、保護か」という二項対立図式とは大きく異なっていたからである。国立保護区が観光資源化されることで、自然や文化を破壊することなく、保護しながらコミュニティを発展させることができる可能性が開かれたのだ。
ケニアの西部州にあるカカメガの森は国立保護区に指定されている。しかしそこでは、その指定に対して反対を表明している人びとが存在している。なぜ彼らは反対するのだろうか。このような疑問を出発点として、本発表では、反対派の論理を明らかにしながら、小さなコミュニティを活性化するための可能性について、従来の人類学的研究とは異なった視点から考察を進めていく。
いかに武力紛争は波及するか
―シエラレオネ・リベリア紛争にみる武装勢力の同盟網―
岡野英之(日本学術振興会特別研究員/大阪大学大学院国際公共政策研究科)
リベリアで紛争がはじまった1989年以降、その周辺国(シエラレオネ、コートディヴォワール)も武力紛争に巻き込まれている。2012年現在でもコートディヴォワール=リベリア国境において武装集団による襲撃事件がしばしば見られる。紛争は国境を越えて拡大し、一国の紛争が終結しても、隣国では紛争が継続する形で長期化している。いかに紛争は国境を越えて波及するかを探るため、発表者はリベリアとシエラレオネにおいて実際に紛争を経験してきた戦闘員や司令官のライフヒストリーを聞き取ってきた。
シエラレオネ紛争(1991-2002年)では、メンデ人により形成されたコミュニティ・レベルの自警組織カマジョー(Kamajor)がカバー(Ahmed Tejan Kabbah)政権によって組織化され政府系民兵として活動した。しかし、クーデターが発生し、カバー政権が亡命すると、カマジョーは軍事政権の打倒とカバー政権の復帰を掲げ、武力闘争を開始する。本研究は、カバー政権が覆された1997年5月から復帰を遂げる1998年3月までのカマジョーの活動を追う。カマジョーはこの頃、自らを強化するためにリベリアとの国境地域を利用した。この頃、リベリアとシエラレオネとをまたがって活動してきたメンデ人が既存の人脈を用いカマジョーを強化していたことがわかる。
国境を越えた紛争の波及には国境を越えた人脈が密接に関わっている。本発表では、ごく短期間に見られたひとつの武装勢力の変化に注目することにより、ひとつの紛争と隣国の紛争が連関しあっている様子を詳細に検討する。
氾濫原をめぐる農民と牧民の対立の回避と協調関係の発展
―タンザニア・キロンベロ谷の事例―
加藤 太(信州大学農学部食料生産科学科/JSPS特別研究員)
近年、サブサハラ・アフリカでは湿地の開発が急速に進められており、水田や放牧地としての利用が進んでいる。タンザニア中南部に位置するキロンベロ谷は、面積約11,600 km2の広大な内陸氾濫原である。ここでは、1980年代以降水田面積が急激に増加したことで、現在では国内コメ生産量の約1割を生産する大稲作地帯が成立した。また、スクマと呼ばれる牧民が放牧地と水田を求めて移住してきたことで、同地域は家畜、特にウシの生産地になった。
同地域は、これまで水田と放牧地が拡大してきたため、もともと居住していた農民と移住してきた牧民の間で土地争いが頻発するようになった。一時は暴力事件を伴う民族集団間の対立が見られる事態になったが、近年は協調関係もみられるようになってきた。
この背景には、両者の間に牛耕を媒介とした関係が構築された点や、中立な意見を言う両者の「老人」が対立する両者の仲裁に当たったことがあげられる。同地域では老人を敬う習慣や家畜の恩恵など、地域に潜在化していた価値観、技術、資源などが必要に応じて顕在化してきたことが対立を回避し、協調関係を発展させることにつながったといえる。
タンザニアにおける遺児の生活状況と教育への影響
中沢美保子(神戸大学大学院国際協力研究科博士課程)
タンザニアではHIV/AIDSの蔓延などにより、遺児(本研究では「少なくとも片親を亡くした18歳未満の児童」と定義する)やその他の脆弱な児童が急速に増加していると言われており、タンザニア本土では約10%の児童が少なくとも片親を亡くした遺児であると考えられている(TACAIDS,2008 Tanzania HIV/AIDS and Malaria Indicator Survey 2007-08)。こうした遺児の社会経済的状況はより脆弱である場合が多く、特に教育に対する影響は深刻な問題である。
一方で、HIV/AIDSの感染が拡大する以前から、タンザニアでは遺児であるか遺児でないかに関わらず様々な理由から親戚が子供を引き取るケースが見られており、遺児が急増する現在もこのような親類のネットワークがショックを吸収していると言われている。このネットワークの存在は、初等教育の就学率に関して遺児とそれ以外の児童との間に大きな差異がないことの理由としてしもしばしば挙げられてきた。
本研究では、2011年12月から2012年3月にかけてタンザニアの大都市及び地方都市で行ったフィールド調査をもとに、このような脆弱な児童に対する包摂の仕組みが、教育との関係の上でどのように機能しているのかを明らかにし、共生のための潜在力について考察する。
焼畑耕作における出作り集落の離合集散と森林資源の共有
-タンザニア南東部の山村の事例-
原子壮太(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科)
タンザニアでは1970年代後半に集村化政策が実施され、山野に散居していた小集落は政府が定める村に集められた。政府はその集住村に社会サービスを整えていったが、財政難によってその体制は間もなく頓挫した。政府は1986年に経済を自由化し、2000年頃からは地方分権化や貧困削減政策をすすめていった。
タンザニア南東部大地溝帯の山麓に位置する調査地でも、焼畑を生業としていた小集落が集められ、様々な民族集団・クランが同居することになった。彼らの生活様式は2年ごとに畑と住居を移動するものであったが、定住化によって集落周辺の林が集中的に開墾されるようになった。これに先立つ1972年頃、この地域に自生するタケが一斉開花し、その種子拡散によって焼畑跡地はまたたく間に竹林に変わった。竹林での焼畑造成には手間がかかるため、彼らは竹林の外側に広がる森林地帯に小さな出作り集落をつくって従来の焼畑耕作を続けていった。2000年代に入ると外部との道路が整備され、僻地の集落にも市場経済が浸透していった。彼らは集住村に屋敷を構え、政府が提供する社会サービスや市場とのつながりを確保しつつ、竹林の拡大によって遠隔地化・狭小化した森林を耕作していった。出作り集落の構成員は流動的で、耕地を移動するたびに離合集散していたが、それは森林資源の共有と、密集した居住にともなう住民間の緊張を緩和するのに貢献していた。
ポスト・アパルトヘイトの南アフリカにおける人種分類の再編成
―華人コミュニティ100年間の経験に注目して―
山本めゆ(京都大学大学院文学研究科博士課程)
アフリカにおける華人という移民マイノリティ集団は、20世紀初頭に初めてのカラーバー導入のきっかけを作るなど、少数者ながら南アフリカ社会と人種政策に影響を及ぼしてきた。民主化以来、南アフリカのエスニック・マイノリティにとっても和解が重要な課題となってきたが、華人もまたアパルトヘイト期の記憶をめぐってコンフリクトの渦中にある。今回の報告では、主にこれまでの文献調査の成果をもとに、南アフリカの人種主義研究において華人に注目する意義について報告したい。とりわけ1)19世紀末以来の華人の地位の変遷、2) 華人コミュニティが「black」に再分類された 2008年のプレトリア高裁判決とその影響に注目する。