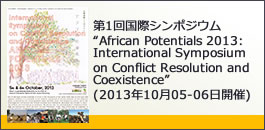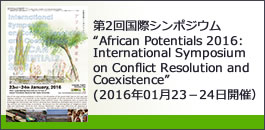- 研究活動
[政治・国際関係ユニット第7回研究会]クロス京子「移行期正義における『和解』のローカル化―ローカルと国際の相互作用の観点から」(2012年11月17日開催)
日 時:2012年11月17日 15:00~17:00
場 所:京都大学吉田キャンパス・総合研究2号館 401号室
プログラム
移行期正義における「和解」のローカル化―ローカルと国際の相互作用の観点から
クロス京子(神戸大学)
報告
南米や東欧の民主化移行期に創出された「移行期正義」という概念は、冷戦終結後には平和構築の視点を絡めた「紛争後の正義」として導入されるようになり、紛争後社会において正義を尽くし和解を実現するためのプロセスやメカニズムとして定義されるようになった。南アフリカ共和国における真実和解委員会の活動以降、各地域のローカル正義に基づく和解制度が移行期正義へ公式に採用される「ローカル化」と呼ばれる事態が、世界各地で進展してきた。本発表では、このローカル化の過程にいかなるアクターが関わってきたのか、ローカル化された和解規範の特徴はどのようなものか、移行期正義がローカル化されることの意義、問題点はなにか、という3点が明らかにされた。とくに、国際規範と国内規範の双方に精通し、活動拠点を国内に持つ「ローカル・エージェント」と、同じく双方の規範に精通し国内外を自由に移動する「トランスナショナル・エージェント」がネットワークを形成し、協働することが、ローカル化の過程で重要な役割を果たしていることに焦点が当てられた。
議論では、「ローカル正義」の「ローカル」とは国際社会の規範に適合する部分だけを抜き取った内容を示しており、「ローカル化」の過程において「ローカルの標準化」、あるいは「ローカルの飼い馴らし(ドメスティケーション)」が進んでいることを強調したほうがいいのではないか、真実委員会の形成過程や機能を考える際には、上述のエージェンシーの動きだけでなく、移行期における国内のパワーバランスをより重視した分析をおこなう必要があるのではないか、「ローカル・エージェント」と「トランスナショナル・エージェント」の間に広がる権力の位相により注意を払う必要があるのではないか、移行期正義の取組みをアフリカへ司法制度を移植する植民地化以降の歴史のなかに位置付ける作業が必要ではないのか、といった指摘がなされた。(佐川徹)
[経済・開発ユニット第4回研究会]金昭延「Between A Rock and Hard Place: South Korean’s Africa Strategies」(2012年11月17日開催)
日 時: 2012年11月17日(土) 15:00~17:00
場 所: 京都大学 吉田キャンパス・総合研究2号館 447室
プログラム
金昭延(リーズ大学、神戸大学)
“Between A Rock and Hard Place: South Korean’s Africa Strategies”
報告
資源開発と資源価格の高騰によるアフリカ経済の隆盛、中国と日本、北朝鮮という東アジアにおける地政学的なポジショニングのなかで、韓国政府が展開してきたアフリカ外交について説明した。韓国からみたアフリカは貿易相手、および援助の対象としてみる傾向がある。2005年には韓国政府はアフリカ・イニシアティブとして援助額を倍増し、2006年には第1回アフリカ・フォーラムを開催し、アフリカ諸国の首脳・代表を招待し、公的機関に対する支援を打ち出した。2009年には第2回アフリカ・フォーラムが開催され、アフリカ連合(AU)重視を打ち出した。そこには、中国や日本のように規模の大きい援助を展開することができず、独自性を出そうとする韓国政府の意図が存在する。2012年の第3回アフリカ・フォーラムでは、治安維持やガバナンスの支援を打ち出し、官民が連携して、積極的に貢献する外交を展開しようとしている。(大山修一)
[第8回全体会議/第3回東アフリカ・クラスター研究会]「紛争のないタンザニア―その要因と展望」(2012年11月17日開催)
日 時:2012年11月17日(土) 10:00~14:30
場 所:京都大学吉田キャンパス・総合研究2号館 4階大会議室(447号室)
プログラム
10:00~10:30:事務連絡
10:30~11:20:根本利通(JATAツアーズ・代表取締役)
「大都市における多民族の混住と紛争回避」
11:20~12:10:伊谷樹一(京都大学アフリカ地域研究資料センター・准教授)
「農村でのもめごとと解決方法(仮題)」
12:10~13:00 昼食
13:00~13:40:中川坦(前駐タンザニア大使、元農林水産省消費・安全局長)
「安定に対するさまざまな懸念―経済成長とニエレレの理想の後退」
13:40~14:30:総合討論
司会:荒木美奈子(お茶の水女子大学・准教授)
要旨
1961年にイギリスからの独立を果たしたタンガニイカは、1964年にザンジバル人民共和国と連合してタンザニア連合共和国(以下、タンザニア)を樹立した。タンザニアの初代大統領となったジュリアス・ニエレレは、1967年の「アルーシャ宣言」において家族的紐帯を基礎としたアフリカ的社会主義を提唱した。これは「ウジャマー」と呼ばれる行政村を単位としつつ、自立と資源の共有を政策の中核に据えながら、争いのない平等な社会の実現に向けて集住化・集団農場の経営・スワヒリ語による初等教育の徹底といった独自の政策を含んでいた。しかし、ウジャマー村政策が実施された1970年代は、頻発する干ばつやオイルショック、ウガンダ戦争などによって国家経済が疲弊し、ウジャマー村政策の推進力は急速に失われていった。そして1985年にニエレレは退陣し、1986年には構造調整計画を受け入れて資本主義経済に政策転換した。
「アフリカの年」以降、相継いで独立を果たしたアフリカ諸国は自立的な国家の建設に取り組んだが、食料自給や経済的自立への道は険しく、貧困や政情不安のなかで政変や民族紛争が繰り返され、タンザニアはそうした近隣諸国からの難民受入国となっていた。タンザニアも連合共和国の成立から今日までのあいだに、さまざまな政策転換や経済体制の変化を経験し、ときにそれは国民に強制的な移住や厳しい経済的困窮を強いることになり、ニエレレが理想とした自立的な国家像からは乖離していった。しかしタンザニアでは、周辺諸国の内紛をよそに、この半世紀のあいだ一度も大規模なクーデターや民族間の抗争は起こっていない。無論、まったく混乱がないわけではなく、ザンジバルでは総選挙のたびに与野党間の武力衝突が起きてはいるが、それが激化・常態化したり、大規模な宗教・民族対立に発展するようなことはなかった。
経済低迷の時代を経て、2000年代中頃からアフリカ諸国は急速な経済成長を見せ始めた。その原動力となったのは地下資源であり、世界的な原油・鉱物価格の高騰と海外資本による資源の開発競争によって大量の資金がアフリカに流れ込んできたのである。タンザニアの経済成長を支えてきた一つは金鉱山であるが、すべての国民がその恩恵を受けてきたわけではなく、むしろそれにともなう物価の高騰や都市中心の政策が地方の経済を圧迫し、かえって経済格差を拡大することになっている。
本会では、過去半世紀のあいだにタンザニアにおいて大規模な紛争が起こらなかったという事実に注目し、その要因を都市・農村・政治の各視点から捉え、制度・規範・慣習・政策のなかに争いを回避する機構を探る。農村社会には日常的なもめ事を鎮静化するローカルな規範が存在し、また多民族が混住する都市社会のなかにも秩序を保つ身体化された暗黙のルールを見ることができる。こうした秩序を維持する機構は政治組織や政策にも反映されているように思える。秩序を保つうえで、タンザニアのミクロとマクロ社会を貫く共通の概念が存在するならば、それはどのようなもので、歴史のなかでどのように育まれてきたのだろうか。そしてそれは、複雑化する現代社会においても有効に機能し続けるのかどうかを検討してみることにする。
「大都市における多民族の混住と紛争回避」
根本利通(JATAツアーズ・代表取締役)
タンザニアという国家が形成された歴史的な流れを宗教・民族・教育制度などの観点から俯瞰するとともに、多くの民族が混住する都市社会において、人々はいかにして対立を回避し、また協調してきたのかを事例を通して分析する。
「農村でのもめごとと解決方法」
伊谷樹一(京都大学)
タンザニアでは法律や条令によって秩序が保たれている。しかし、農村社会には現代法では解決できない複雑な問題も多々存在し、彼らはそれを慣習的な方法で解決してきた。本会では、タンザニアの農村社会に潜むいくつかの問題を取り上げ、それへの農民の対処について報告し、農村で見られる対立の回避機構について検討する。
「安定に対するさまざまな懸念―経済成長とニエレレの理想の後退」
中川 坦(前駐タンザニア大使、元農林水産省消費・安全局長)
資源のない「平等に貧しい社会」では国民の不満も昂ぶらず、社会は低位に安定していたといってよい。しかし、2003年以降、世界的な地下資源価格の高騰によってタンザニアの経済は急速に成長し、経済的な格差が一気に顕在化してきた。ニエレレが理想とした平等な社会は、経済偏重の流れのなかで後退しつつある。タンザニアが育んできた「争いを未然に防ぐ制度や体制」は、グローバル化社会においても不安定要素を解消する機能を保持できるのか、今後のガバナンスの動向を見ながらこの国の将来を展望する。
[北東アフリカ・クラスター第3回研究会]橋本栄莉「『紛争』と『解決』の文化装置再考―南スーダン、ヌエルの予言者の歴史的生成過程と現代の牧畜民紛争」(2012年11月16日開催)
日 時:2012年11月16日 16:30~18:30
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階301号室
プログラム
「紛争」と「解決」の文化装置再考―南スーダン、ヌエルの予言者の歴史的生成過程と現代の牧畜民紛争
橋本栄莉(一橋大学)
報告
南スーダンにくらすヌエルの予言者が、歴史的にいかなるまなざしによって成立し、規定されてきたのか、そして現代の紛争時に予言者がいかなる役割を果たしているのかを分析した。発表ではまず、「紛争の仕掛け人としての予言者」という認識がいかに創出されたのかを、植民地行政官らによる予言者をめぐる記述から分析するとともに、その同じ予言者がヌエルの人びとからは「平和構築者」として想起されてきたことを示した。つぎに、2011~2012年に発生したロウ・ヌエル―ムルレ間の武力衝突の際に登場した自称予言者を、異なる立場にあるアクターがそれぞれいかなる存在として位置付けているのかを明らかにした。最後に、ヌエルにおける予言者は、多様なアクターが紛争を事後的に理解するための文化装置として、また紛争の「解決」方法を考えるための物語を編成する文化装置として作用していることを論じた。
議論では、予言者のヌエル社会における社会的地位はいかなるものであるのか、予言者は実際の紛争の動員過程でいかなる役割を果たし(たとえば分節出自を越えた動員をおこなっているのか)、また平和構築の現場にどのように巻き込まれているのか、過去の予言者のことばがいかにテキスト化され利用されているのか、予言者とキリスト教はどのような関係にあるのか、文化装置やまなざしという語を用いることがこの研究対象を分析するにあたって有益なのか、といった質問がなされた。(佐川徹)
[第9回公開ワークショップ]Kate Meagher「Taxing Times: Informal Economies and Religious Conflict in Northern Nigeria」(第9回Kyoto University African Studies Seminar (KUASS)との共催、2012年11月16日開催)
日 時:2012年11月16日(金)15:00~17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室
演題:「Taxing Times: Informal Economies and Religious Conflict in Northern Nigeria」
発表者:Dr. K. Meagher(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)
※講演は英語でおこなわれます。
要 旨: This lecture is based on research carried out in northern Nigeria in late 2011, just before the acceleration of terrorist bombing. It examines the role of informal economic activities, which in Nigeria tend to be based on ethnic and religious forms of organization, in exacerbating or mitigating religious conflict. The lecture focuses on three categories of informal activities, characterized by economic interdependence, competition and value conflicts between Christian and Muslim enterprise groups. It examines how the nature of informal economic relations influences inter-religious relations between each of these three categories of enterprises, and considers how government policy contributes to strengthening or undermining positive tendencies, or exacerbating negative processes. In the process, the lecture reveals the underlying basis of religious tension in northern Nigeria, and the social resources available to address it.
[生業・環境ユニット第5回研究会/第8回公開ワークショップ]根本利通「タンザニアの国民意識の形成」(第191回アフリカ地域研究会、2012年11月15日開催)
日 時:2012年11月15日 (木)15:00〜17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階318室
プログラム
「タンザニアの国民意識の形成」
根本利通(Japan Tanzania Tours Ltd.)
要 旨
1885年のベルリン会議によって分割されたアフリカ大陸では、多民族の住む地域に国境線が与えられた。この各植民地が独立し、国民国家の形成を目指す中、その多くが民族紛争を繰り返すことになった。しかしタンザニアは独立50周年を過ぎ、大きな民族対立、内戦を経験せずにきている。タンザニアの近現代を19世紀半ばから振り返ってみたい。
[第8回公開ワークショップ/生業・環境ユニット第5回研究会]根本利通「タンザニアの国民意識の形成」(第191回アフリカ地域研究会、2012年11月15日開催)
日 時:2012年11月15日 (木)15:00〜17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階318室
プログラム
「タンザニアの国民意識の形成」
根本利通(Japan Tanzania Tours Ltd.)
要 旨
1885年のベルリン会議によって分割されたアフリカ大陸では、多民族の住む地域に国境線が与えられた。この各植民地が独立し、国民国家の形成を目指す中、その多くが民族紛争を繰り返すことになった。しかしタンザニアは独立50周年を過ぎ、大きな民族対立、内戦を経験せずにきている。タンザニアの近現代を19世紀半ばから振り返ってみたい。
[政治・国際関係ユニット第6回研究会 & 西アフリカ・クラスター第4回研究会]Kate Meagher「The Strength of Weak States?: Hybrid Governance and Non-State Security Forces in Nigeria and the Congo」(2012年11月09日開催)
日 時:2012年11月9日(金)18:00~19:30
場 所:東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム3
プログラム
18:00~19:30
Kate Meagher (London School of Economics and Political Science)
ケート・ミーガー(ロンドン政治経済学院)
“The Strength of Weak States?: Hybrid Governance and Non-State Security Forces in Nigeria and the Congo”
「弱い国家の強さ―ナイジェリアとコンゴにおけるハイブリッドなガバナンスと非国家保安部隊」
要旨
This lecture will look at whether non-state security forces (vigilantes, militias, etc.) can provide a second-best source of security in fragile regions. It starts with a critique of new ‘hybrid governance’ approaches to state-building, which encourage the integration of informal security arrangements into state structures. This sets the scene for a comparative analysis of the Bakassi Boys of Nigeria and the RCD-ML militia in the Eastern DRC, which challenges the notion that informal security arrangements necessarily enjoy local legitimacy, and raises questions about their potential for improving the governance context even if they start out as locally legitimate forces.
[社会・文化ユニット第7回研究会]石田慎一郎「おそろしい隣人:ケニア・ニャンベネ地方40世帯10年の事件簿」、近藤英俊「敵対・同盟関係と妖術の『効果』」(2012年10月27日開催)
日 時:2012年10月27日(土)
場 所:首都大学東京南大沢キャンパス国際交流会館1階中会議室
プログラム
13:00~14:50
石田慎一郎(首都大学東京)
「おそろしい隣人:ケニア・ニャンベネ地方40世帯10年の事件簿」
15:00~17:00
近藤英俊(関西外国語大学)
「敵対・同盟関係と妖術の『効果』」
報告
石田氏は、ケニア中央高地ニャンベネ地方の一集落における独自の紛争処理について論じた。この地方では近年土地が希少となり、1989年の土地登記事業開始以降、人びとが土地をめぐる権利意識を変化させ、土地所有に大きく関わるクランの役割もそれに伴い強化されてきた。そのような状況下、集団間同盟(イシアロ)=「おそろしい隣人」が紛争処理に利用されている。1つのクランに対し、特定の2つのクランがイシアロ関係となっており、イシアロには相互扶助や信義誠実が要求され、背くと制裁される。石田氏は、人びとがこの関係を利用し、個人間の争いなどでイシアロを使って宣誓や呪詛で解決を図ったり、賠償のとりたてを行っていることを指摘し、「官」や「専門家」に依存しない当事者同士の紛争処理が行われていることを、10年の事件簿を通して明らかにした。
近藤氏は、北ナイジェリアの都市カドゥナにおける、ある呪術師一家に起こった5つの事件(近藤氏自身が巻き込まれたものを含む)を取り上げ、グローバル化のなかでの平準化や蓄財といった妖術論を超え、当事者にとっての妖術がいかにリアルであるのかを例証した。家の主人で妖術師の男性は、一見ささいにも思えるネガティブな偶然の重なりに次々と妖術のラベルを貼り、出来事としての終止符を打っていく。それは彼にとって、わからなさ、不確実性を解決する手段でもある。当事者にとって、すべての出来事が必然だと感じられていく、つまり偶然性と必然性が重なり、妖術へと結びついていく過程とメカニズムが詳細に論じられた。また、その背景に、言語、宗教、民族的に「超多文化」であるカドゥナという都市社会の影響があることが示唆された(平野(野元)美佐)。
[第2回アフリカの紛争と共生セミナー](2012年10月20日開催)
日 時:2012年10月20日(土)13:30~18:00
場 所:京都大学稲盛記念館3階小会議室I
プログラム
13:30~14:35
岡野英之(大阪大学国際公共政策研究科)
武力紛争経験国における国家とローカルな社会秩序の維持―シエラレオネを事例として―
14:35~14:45 休憩
14:45~15:50
藤井真一(大阪大学人間科学研究科)
紛争解決と/の人類学―ソロモン諸島の「民族紛争」から
15:50~16:00 休憩
16:00~17:05
伊東未来(大阪大学人間科学研究科)
ニジェール河内陸三角州における生業と民族
17:05~18:00 総合討論
要旨
武力紛争経験国における国家とローカルな社会秩序の維持―シエラレオネを事例として―
岡野英之(大阪大学国際公共政策研究科)
現在の世界において国家からの影響は避けることができない。ローカルな社会秩序の維持も例外ではない。本発表では、紛争前・紛争中における社会秩序の解体や疲弊、それに連続する紛争後の社会秩序の回復が、国家といかに関わっているのかを論じていく。なお、本研究ではシエラレオネ農村部における社会秩序を事例として扱う。
紛争解決と/の人類学―ソロモン諸島の「民族紛争」から―
藤井真一(大阪大学人間科学研究科)
本報告では、紛争解決(conflict resolution)と人類学とがどのように関連付けられてきたかを整理する。次いで、ソロモン諸島で生じた「民族紛争」と紛争解決の動きを紹介する。最後に、ソロモン諸島における紛争後社会の再構築をめぐる諸事例を通じて、紛争解決と/の人類学の可能性について考える。
ニジェール河内陸三角州における生業と民族
伊東未来(大阪大学人間科学研究科)
ニジェール河内陸三角州に生活する複数の民族、とりわけ牧畜をになうフルベと農業をになう諸集団の関係に焦点をあてる。彼らがすみ分けや資源の共有をいかにおこなってきたのか、問題が起きたときいかに解決をはかってきたのか、ここ30年年あまりの干ばつや市場の変化は両者の関係にどのような変化をもたらしたのか、などを明らかにする。