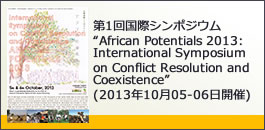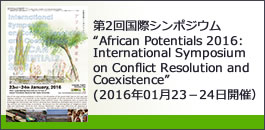- 研究活動
[第7回全体会議]「今後の研究方針の打ち合わせ」(2012年07月14日開催)
日 時:2012年7月14日(土)10:00~12:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階小会議室
今回の全体会議では、各ユニットとクラスターの世話人と副世話人があつまり、今後の活動方針に関して、以下の議論をおこなった。
議題
(1)本プロジェクトの成果を国際的、国内的に発信するために、どのような道があるか。
- 「ヨーロッパ・アフリカ会議」(2013年6月、ポルトガル:パネルの締め切りは2012年10月19日)
- 「アメリカ・アフリカ学会(2013年11月、締め切りは2013年3月)」
- 「カナダ・アフリカ学会(2013年5月)」
- 「2013年京都国際地理学会議:地球の将来のための伝統智と近代知(2013年8月、関連学会とのジョイントセッション[20分の発表を4つ]の締め切りは2012年8月末)」
- 「アメリカ・人類学会(2013年11月)」
- 「IUAES(International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)のInter-Congress(2014年5月)」
- 「日本アフリカ学会(2013年5月:東京大学開催)」
(2)学会誌そのほかで、特集を組むかたちで成果の発表ができないか。
(3)2013年度には、日本で国際シンポジウムを開催するが、その開催地と時期をどうするか。
(4)2013年度の「アフリカ・フォーラム」をどこでやるか。
(5)「データ・アーカイブ」にデータをどのように集積するか。
報告
(1)第2回「アフリカ紛争・共生フォーラム」は、2012年12月8~9日にハラレで開催するが、発表者は、アフリカ人、日本人ともにほぼ確定した。
(2)今年度の若手研究者派遣について。(太田至)
[社会・文化ユニット第5回研究会]内藤直樹「排他的領域性を超えるローカルな実践」、木村大治「コンゴ民主共和国ワンバにおける『土地をめぐる権利』の諸相—日常的利用、歴史的所有、自然保護区」(2012年07月07日開催)
日 時:2012年7月7日 15:00~18:15
場 所:京都大学稲盛記念館3階小会議室1
プログラム
15:00〜16:30
内藤直樹(徳島大学)
「排他的領域性を超えるローカルな実践」
16:45〜18:15
木村大治(京都大学)
「コンゴ民主共和国ワンバにおける『土地をめぐる権利』の諸相—日常的利用、歴史的所有、自然保護区」
報告
内藤氏は、まずケニアにおける先住民運動や選挙後暴力を事例に、近年の土地と文化の結びつきの強化が文化的他者に対する排除を強化している傾向を指摘した。そしてケニア政府が排他的な難民庇護政策を実施するなかで、東部のダダーブ難民キャンプのソマリ系長期化難民が、携帯電話やインターネットなどのニューメディアを活用してケニア市民をはじめとする外部世界の人々との間に築きあげた諸関係をどのように理解するべきか議論を行った。質疑応答では、国境を越えて分布するソマリのネットワークが、難民の生活世界の再編にどのように影響しているのかという質問や、ケニアの難民のようなシティズンシップを剥奪された状況にある人々をはじめとする国家と人々との多様な結びつきのあり方をどのように考えるのかついて議論が繰り広げられた。
木村氏はコンゴ民主共和国(旧ザイール)のワンバで生活するボンガンドの人々の生業活動や、土地利用の概要を述べた後、近年、自然保護区が設定されるプロセスのなかで生じている紛争の背景には、ボンガンドの人々の移住の歴史や、リネージ同士の対立があることを提示した。質疑応答では、森の利用方法に明文化されたルールがあるのか(あったのか)、自然保護区以外に関する紛争が生じた場合には、集団間でどのような解決方法が採用されているのか(きたのか)、紛争の主体となっている単位が、近年作られたものである可能性や、実は以前から外部と頻繁に接触し、交渉に長けた人々である可能性、町から帰ってきた人々が近年のリーダ的存在になっている可能性、内戦中に交渉する術を学んだ人々である可能性などが考えられ、ボンガンドの人々が経験してきた詳細な歴史を明らかにする必要があるという点が確認された。(伊藤義将)
[政治・国際関係ユニット第4回研究会]佐川徹「東アフリカ牧畜社会における地域紛争と自警団」(2012年05月12日開催)
日 時:2012年5月12日(土) 15:00~17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館 小会議室II
プログラム
東アフリカ牧畜社会における地域紛争と自警団
佐川徹(京都大学)
報告
2000年代に入ってから、アフリカ大陸では国家規模で展開する大規模な内戦の数は減少しているが、資源の争奪などをめぐって発生するより小規模な「社会紛争」は発生し続けている。東アフリカ牧畜地域における紛争はその典型例として挙げられる。発表ではまず、エチオピアとケニアの国境付近に位置する牧畜社会で、政府や非政府組織による平和構築を目的とした介入が十分な成果を挙げておらず、むしろ中央政府主導の大規模な土地開発によって、多くの新たな紛争の種が蒔かれていることが指摘された。つぎに、タンザニアやケニアで、住民と公的部門の連携のもとに地域の治安向上に一定の成果を挙げてきた、自警団スングスングの活動について紹介がなされた。スングスングは1980年ごろにタンザニアのスクマやニャムウェジの人々が自生的に形成し、犯罪の取り締まりや処罰の決定に効果を発揮し、しばらくのちにタンザニア政府も公的にその活動を認可し、さらには国境を越えてケニアにまでその活動が広がった。しかし、ケニア南西部のクリアではスングスングが次第に犯罪集団化し、現在では政府の治安部門改革の一環として実施されているcommunity policingの活動にとってかわられていることが示された。
討論では、スングスングのメンバーが治安維持に従事したもともとのインセンティヴとそのメンバーが犯罪集団化していった理由について、治安維持に関わるアクターへの報酬と関連づけながら議論がなされた。また、non-state actorの治安維持への関与はOECD-DACなどによっても推進されているが、それについて論じる際には、ともに「治安維持活動」に従事しているとはいっても、対外的な防衛活動を担う組織と日常的な犯罪行為を取り締まる組織とは分けて論じる必要があるのではないか、との指摘もなされた。さらに、自警団のような組織は、政府がその活動を事後的に承認して法制度化されたか否かを評価の対象にするのではなく、その活動が必要になったときにそれに応じて組織が自生的に生成し、また必要がなくなったら消えていくというアドホックな側面を評価の対象にすることもできるのではないか、という点も論じられた。(佐川徹)
[経済・開発ユニット第3回研究会]片柳真理「アフリカにおける紛争予防と開発―アイデンティティ集団の意識を考える―」、峯陽一「南アフリカとジンバブエ—不平等、紛争、政治制度の比較—」(2012年05月12日開催)
日 時: 2012年5月12日(土) 15:00~17:30
場 所: 京都大学稲盛記念館 3階 小会議室I
プログラム
片柳真理(JICA研究所)
「アフリカにおける紛争予防と開発―アイデンティティ集団の意識を考える―」
峯陽一(同志社大学)
「南アフリカとジンバブエ—不平等、紛争、政治制度の比較—」
報告
片柳氏と峯氏は現在、JICA研究所で実施している「アフリカにおける暴力的紛争の予防—開発協力が果たす役割」という研究プロジェクトのメンバーであり、本発表では、そのプロジェクトの基本的構想、および現在までの成果が紹介された。
片柳氏は、文化的集団間の不平等を水平的不平等(HI: Horizontal Inequality)と捉え、多次元の水平的不平等は紛争を誘発しやすいため、客観的・主観的な水平的不平等を拡大させない政策が必要であり、政治家は言動に注意する必要がある点を述べた。議論としては、水平的不平等とは民族間の不平等であり、このような調査を行うことによって、民族間の紛争を悪化させることはないのかという質問が出されたが、片柳氏はネパールで開発を行うアクターが水平的不平等を意識しながらプロジェクトを行ったために成功した事例がある点を強調した。また、民族集団の母数がわからないなかで、どのようなサンプリングによって現地調査が行われたのかという質問に対して、峯氏からは、正確な統計データが存在する都市部に調査地を限定し、ランダムにサンプリングを行ったと回答があった。峯氏からはまた、プロジェクト全体の考え方として、HIを分析することですべてが解決するとは考えていないが、ある集団をどのように見るのかという視点の1つとして、HIを採用しながら、統計分析とケーススタディを行っている点が説明された。また、アフリカ諸国のうち対照的な政治体制をもつ国々(例えば、南アフリカとジンバブウェ、ウガンダとタンザニア、ガーナとコートジボワール、ルワンダとブルンジ)の比較を行っている点が特徴的であることが説明された。
峯氏の発表では、南アフリカとジンバブウェのパワーシェアリングについて行った調査結果が紹介された。小さな政党が暴力によって政権を不安定にさせる能力があるうちは、複数の大きな政党によるパワーシェアリングは有効であるが、ジンバブウェの事例を見る限り、それが長年続くことによって、さまざまな政治的問題がエリートたちの間だけで決定されるようになり危険であることが報告された。また、小選挙区制の選挙では、勝者が全権を握るという民意とかけ離れた結果を招いてしまうため、文化的・社会的背景が多様な国民で構成される国の実態には適合しないこと、そのような国では比例代表制選挙が効果的であるが、その欠点としては、政治家が政党内部でどれだけ力を得るかということに意識を集中させ民意を無視してしまう傾向があることが述べられた。結論としては、永続的に完全な選挙制度などは存在せず、状況に応じて選挙制度が変わることが望ましいということだった。議論としては、選挙制度と行政を一体と捉えて、この二つがあたかも同じ動きをするように語ることに対して疑義が出されたが、今回のプロジェクトにおいては、その点は議論をしていないため、今後検討していく必要があることが確認された。(伊藤義将)
[第6回全体会議]「大きな紛争から小さな”日常的”紛争へ?:住民参加の導入とアフリカの自然保護戦略の変容」(2012年05月12日開催)
日 時:2012年5月12日(土)10:00~14:45
場 所:京都大学 稲盛記念館 3階 中会議室
プログラム
10:00~10:15 事務連絡
10:15~10:30 山越言(京都大学) 「趣旨説明」
10:30~11:30 關野伸之(京都大学) 「住民対立を増幅させる住民参加型資源管理―セネガルの事例から」
11:30~12:30 大沼あゆみ(慶應義塾大学) 「自然資源の保全インセンティブに関わる利益配分の諸形態と効果」
12:30~13:15 休憩
13:15~14:15 大村敬一(大阪大学) 「『自然=社会多様性』を目指して―グローバル・ネットワークに抗するイヌイト」
14:15~14:45 総合討論
報告
趣旨説明 山越言(京都大学)
アフリカにおける環境保護をめぐる近年の潮流、国家主導型保護政策の多様化と経済原理の導入などを紹介したうえで、アフリカにおける自然資源保護の権力と政治性、地域住民への影響とその対応を検証することの重要性が報告された。近年の研究が、環境政策に対する分析とともに、住民対応というミクロな視点をもつという特徴がある。
住民対立を増幅させる住民参加型資源管理―セネガルの事例から
關野伸之(京都大学)
セネガルの漁業と海洋保護区の設立の歴史を紹介したうえで、B共同体海洋保護区における国と地域共同体組織の共同管理、生物多様性保全と地域開発の両立をめざす設立の目的が説明された。この海洋保護区における禁漁区の設置のあり方に対する意見の対立があり、海洋保護区に設立されたエコロッジは地元住民の雇用効果を生まず、不適切な経営、利益分配をめぐる争い、運営委員会の不透明な金の流れが問題となり、経済効果が疑問視されている。環境NGOがマスメディアや企業と連携すると同時に、地方議会への議員の選出など、政治に積極的に参加し、植林プロジェクトを展開している。フランス系の企業による資金提供によって、気候変動対策として、2009年現在、3670万本のマングローブ林の植林がおこなわれた。数字上は成功したとされるが、内実は失敗とされ、評価が分かれている。この植林プロジェクトを契機としてNGOが分裂し、NGOどうしが競合している。マングローブ海域の象徴種であるThiof(ハタの1種)を利用し、海洋保護区の設置によって、個体数の増加が成果として考えられているが、その評価についても意見が分かれている。援助プロジェクトでは、友人どうしのつながりでプロジェクトを動かし、住民のあいだで資源へのアクセスの不平等と不満が生まれている。共同体海洋保護区の設立によって、グローバルやナショナルな人脈とむすびついて、ローカルな紛争が発生し、その紛争が増幅させている実情が示され、試行錯誤を繰り返しながら、対立の現場から解決策を模索する姿勢が重要とされている。
自然資源の保全インセンティブに関わる利益配分の諸形態と効果
大沼あゆみ(慶應義塾大学)
共同体ベースの環境保全(CBM)では、住民が主体となって自然資源や環境保全に取り組むことが重要である。CBMの分類として、市場の利用(商業的/非商業的)、資源採取の有無(採取的/非採取的)によって4分類に分けることができる。便益の強さとしては、商業的>非商業的、採取的>非採取的となる。金銭によるインセンティブは強く、供給量を調整することで、金銭的なインセンティブを作り出すことができる。ただし、市場の不確実性が存在することで、需要の大きさが変動し、便益の安定性に影響を及ぼす。監視にかかる報酬の定額配分では、監視努力が低く、報酬が低い場合には、その保全活動は失敗する傾向にある。監視努力の費用の増加よりも、収入の増加が大きいときには、住民の選好順位は上昇する。ジンバブエにおけるCAMPFIREのサファリハンティング収入では、ハンティング収入が大部分を占め、その6割はゾウのハンティングであった。収入の50%を地域に還元し、地域住民は生活インフラの整備に充当した。CBMでの実現可能性は、コミュニティーのガバナンスの質が重要である。発生する現金収入の利益の配分には、倫理的な配分基準が関係し、それほど簡単にはいかない。貢献に応じた支払いが生産量を最大化させることが示された。
「自然=文化多様性」を目指して―グローバル・ネットワークに抗するイヌイトの選択
大村敬一(大阪大学)
大村氏は、まず極北ツンドラ地帯にくらす先住民イヌイトの先住民運動の歴史をふりかえった。先住民運動に積極的に関与して近代国家内部で「成果」を勝ち取ることは、主流社会、つまり「白人のシステム」への同化を促進することにつながる可能性もある。しかしイヌイトは、グローバル・ネットワークに部分的に取り込まれながらも、完全にそこへ吸収されずに、「イヌイト」でありつづけてきた。それは彼らが、グローバル・ネットワークでの生き方とは異なる「イヌイトの生き方」、その生き方を支える動物と人間の交歓に支えられた生業システム、そして人間と非人間から構築される自然=文化の多様性を、運動の過程で守りつづけてきたからである。大村氏は最後に、イヌイトが目指す統治のあり方として、「近代のデモクラシー」にくわえて、モノにまで拡張した民主主義、すなわち「モノの議会」の創設についての構想を論じた。
(大山修一・佐川徹)
[北東アフリカ・クラスター第2回研究会]伊藤義将「『長老』が仲介する紛争解決方法」(2012年05月11日開催)
日 時:2012年5月11日(土) 16:00~18:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館 中会議室
プログラム
『長老』が仲介する紛争解決方法
伊藤義将(京都大学)
報告
エチオピアでは「長老」と呼ばれる人々が紛争を仲介する方法が広範囲で見られる。エチオピア西部のジンマ市周辺に居住するマチャ・オロモとエチオピア中央高地に居住するアルシ・オロモの人々は、ジャールサ(jarsa)と呼ばれる人物が紛争を仲介している。ジャールサとはオロモ語で「長老、高齢者、老人」という意味の言葉であるが、紛争の仲介を行うジャールサは必ずしも長老であったり、高齢者であったりするわけではない。現地の人々は世帯を持つ成人男性はみなジャールサになれると言い、紛争の内容に応じてその問題を解決するにふさわしい人物がジャールサに選ばれる。例えば、土地の境界をめぐる紛争であれば、その土地の近くに長く住んでいるものや、以前その土地を保有していた者がジャールサとなる。
エチオピアのオモ川流域に住むアリの人々も同じような方法でガルタと呼ばれる人物が紛争を仲介している。ここでもガルタ(galta)という言葉に「老人」という意味があるが、仲介者が必ずしも老人や高齢者ではなく、紛争の内容によって適当な人物がガルタに選ばれているという。
これまでの事例と少々異なるのは、エチオピア中南部に住むデラシェの仲介者であった。小さな紛争はアト・モラ(ato mola)と呼ばれる老人が紛争を仲介するが、人の生死に関わる大きな紛争については、ショルギア(shorgia)と呼ばれる人物が仲介する。ショルギアの判決は絶対であり、みなが従うという。ショルギアとは経済的に豊かである世帯の長であり、凶作のときなどに人々の生活を支えるという。男性世帯主であれば誰でもジャールサやガルタになれるオロモとアリの事例とは異なり、ショルギアとして認識されている人々はこの地域に4名しかいないという。
近年の外部からの影響が紛争の解決方法に強く反映されているのは、エチオピアの中央高地に居住するシダマと南部の山岳地域に居住するマーレであった。シダマにも「長老」が仲介する紛争解決方法は存在するが、土地をめぐる紛争に関しては、行政村の長に相談するという。そこで解決しない場合には群の長が問題を取り扱うという。その背景には多くの土地が近年に現金で購入された土地であり、政府の書類にその売買の記録が残されているからだという。マーレにおいてはプロテスタントが強い影響を与えていた。マーレでは仲介者をカイジョ(kayjo)と呼び、従来はガルチ(galchi)(=老人)がカイジョになっていたという。しかし近年カイジョになるのはプロテスタント教会の有力者であるチンモ(chimmo)と呼ばれる人々であるということであった。
発表では、次にマチャ・オロモで仲介が行われ、表向きには紛争が解決されたように見えても、当事者同士の社会関係が悪化したという事例が示された。しかし、その紛争解決のプロセスにほとんど関わることのない女性が、世帯間の関係を維持する努力をしているなど、より大きな紛争へと発展しないように紛争の激化に歯止めをかけている可能性が示唆された。
最後に議論のなかで、紛争を仲介する人と当事者の関係や、村全体の社会関係を詳しく調査し提示する必要がある点が指摘された。また、北東アフリカ・クラスターの今後の展望として、北東アフリカ地域で行われている紛争解決方法にはどのような多様性があるのか(または、ないのか)、北東アフリカの異なる地域の専門家を招いて、その地域で行われている紛争解決方法について紹介してもらい、議論を深めていくことが提案された。(伊藤義将)
[南部アフリカ・クラスター第2回研究会]大山修一「ザンビアにおける土地法の改正とベンバ社会の混乱」(2012年5月11日開催)
日 時: 2012年5月11日(金)
場 所: 京都大学稲盛記念館 3階 小会議室Ⅱ
プログラム
「ザンビアにおける土地法の改正とベンバ社会の混乱」
大山修一(京都大学)
報告
報告では、1995年に施行された新・土地法によって、土地保有証明書が強化され、外国人の土地保有に規制が緩和されるとともに、土地の権利については各地域や民族のチーフに大きな裁量がもたらされることになったこと、ザンビア北部で焼畑農業を続けてきたベンバ社会においても、この法律に起因してさまざまなタイプの土地の囲い込みが生じ、自給的農業の持続性が危機的状況におかれていることが論じられた。
討論では、新・土地法とそれに基づく制度が強い力を発揮する局面と、むしろそれが無効化される局面がありうることが議論された。とりわけ土地の囲い込みを認めるか否かや、その方法や手続きのあり方には、チーフの個人的資質や経験が、大きく影響していることに関心が集まった。そのために制度的に「混乱」が生じたり、不平等感を感じる人びとがいる一方で、チーフさえ交代すれば土地をめぐる社会状況も大きく変わりうるという可塑性によって、権力や富の集中といった一方向的な展開が避けられている側面があることも指摘された。また外国資本の参入や都市住民などによる「土地収奪」問題は、アフリカ全体に通じる今日的課題であり、それによって生じる紛争とその解決について広範囲から議論を深めることの重要性も確認された。(津田塾大学 丸山淳子)
[第5回全体会議]「今年度の活動の総括と次年度に取り組むべき課題」(2012年03月29日開催)
日 時:2012年3月29日(木)10:00~14:30
場 所:京都大学 稲盛記念館 3階 中会議室
プログラム
10:00-10:30
事務連絡
10:30-11:30
「アフリカ紛争共生フォーラム(ナイロビ)の報告と議論のまとめ」
松田素二(京都大学)、栗本英世(大阪大学)
11:30-12:30
質疑応答
13:10-14:10
「政治・国際関係ユニット」の活動報告
遠藤貢(東京大学)、武内進一(JICA研究所)
「経済・開発ユニット」の活動報告
高橋基樹(神戸大学)
「生業・環境ユニット」の活動報告
山越言(京都大学)
「社会・文化ユニット」の活動報告
松田素二(京都大学)
14:10-14:30
来年度にむけて事務局からユニットとクラスターへのお願い
報告
今年度最後の全体会議では、まず松田素二氏と栗本英世氏が、2011年12月2日から4日にかけてナイロビで開催された「アフリカ紛争・共生フォーラム」の内容と成果を報告した。フォーラムに参加したアフリカ人の研究者や活動家にとって、「アフリカの潜在力を用いて紛争を解決する」という考えは常識であり出発的である、という認識が確認されたとともに、フォーラムでの議論の対象は、その潜在力を実践で活用するときに直面する困難にどのように対処すればいいのか、という点に置かれていたことが報告された。また、アフリカの出席者からは、このフォーラムにより「紛争と共生」をめぐる論点がクリアになり有意義だったという評価が多く、次年度からの「アフリカ紛争・共生フォーラム」でも、今回のフォーラムで議題となった内容をベースに議論を進めていけばよいのではないか、そして、今回の参加者の一部には今後も本プロジェクトにかかわってもらい、次回以降のフォーラムにも参加してもらうことが望ましいのではないか、という指摘された。
次に、「政治・国際関係」「経済・開発」「生業・環境」「社会・文化」ユニットの各世話人(ただし「政治・国際関係」ユニットは遠藤貢氏が欠席のため、代理で武内進一氏)から、今年度の活動内容とそこから浮かび上がってきた論点について報告があった。それに対して代表者の太田至氏から、次年度以降、各ユニットに重点的に取り組んでもらいたい課題が提示された。(佐川徹)