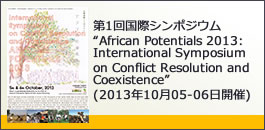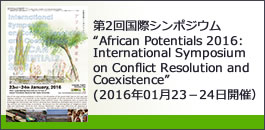- 研究活動
[生業・環境ユニット第2回研究会]「アフリカ自然保護の潮流:原生自然保護から住民参加型保全、そして新自由主義へ?」(第2回アフリカ自然保護研究会との共催、2011年11月06日開催)
日 時:2011年11月6日(日)
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室 (第2回アフリカ自然保護研究会と共催)
プログラム
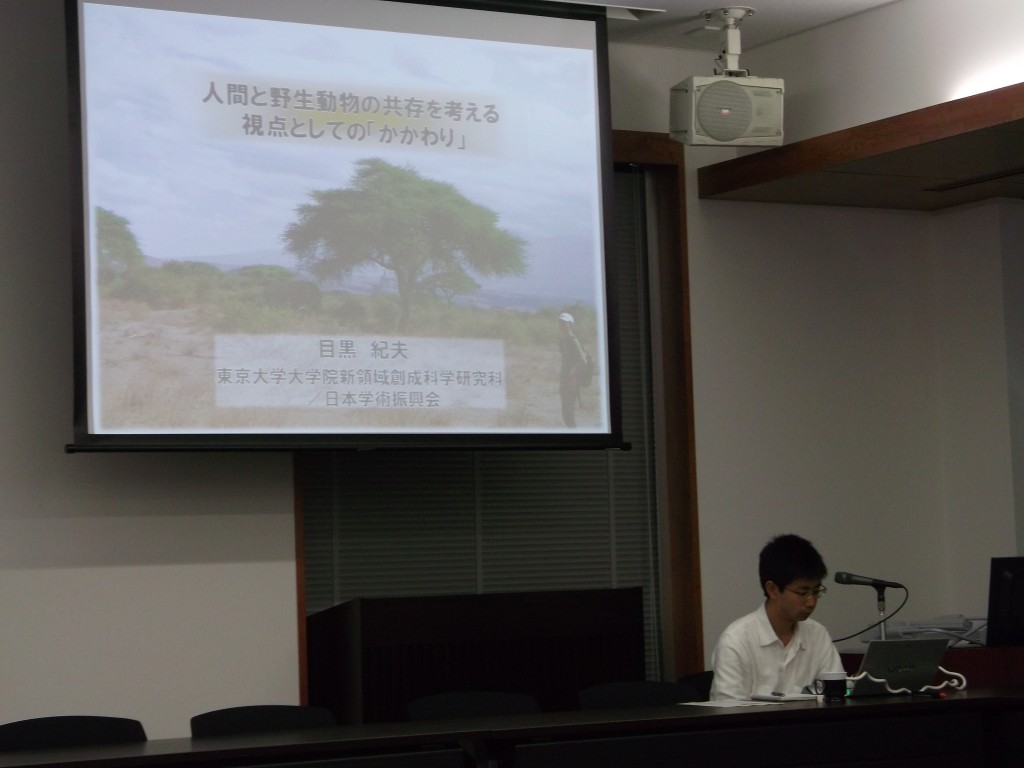
趣旨説明『日本におけるアフリカ自然保護研究史』
13:45-15:00 目黒紀夫(東京大学) 『人間と野生動物の共存を考える視点としての「かかわり」』
15:00-15:30 コーヒーブレイク
15:30-15:45 池野旬(京都大学) 『コメント』
15:45-16:30 討論 (これからの自然保護研究の方向性について)
発表要旨
『人間と野生動物の共存を考える視点としての「かかわり」』 目黒紀夫(東京大学)
1990年代以降、アフリカの野生動物保全では「コミュニティ主体の保全」が 新たな保全パラダイムとして位置づけられるようになった。しかし、一言に 「コミュニティ主体の保全」といっても、そこには少なくとも、功利主義的 な「便益アプローチ」と新自由主義的な「権利アプローチ」そして熟議民主 主義の流れを汲む「対話アプローチ」の3つの潮流が確認できる。そして、 それらのアプローチは経済的便益や私的権利、対話の機会を実現することで 「保全」が「成功」すると想定しているが、そこではローカルな人間と野生 動物のかかわり(の多様性・地域性)はまったくといっていいほどに考慮 されていない。 本発表では、ケニア南部アンボセリ生態系のマサイ社会において90年代以降 に取り組まれてきた複数の「コミュニティ主体の保全」を事例として、上述 の各アプローチの妥当性を検討するとともに、ローカルな「かかわり」を 見ることの重要性(見ないことの問題性)を考えていきたい。


[生業・環境ユニット第1回研究会]「タンザニア農村における対立回避のメカニズム」(2011年10月29日開催)
日 時:2011年10月29-30日
場 所:長野県下伊那郡阿智村・中央公民館 会議室
プログラム
10月29日(土)
13:00 伊谷樹一(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・准教授)
趣旨説明
13:15 伊谷樹一 住民間の対立を調停する組織・ワゼーワミラ
14:15 黒崎龍悟(福岡教育大学教育学部・講師)
対立回避の事例報告:ルヴマ州ムビンガ県キンディンバ村
15:15 荒木美奈子(お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・准教授) 対立回避の事例報告:ルヴマ州ムビンガ県キタンダ村
16:15 原子壮太(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・研究員) 焼畑共同耕作グループの解散と再編
17:15 近藤史(神戸大学大学院農学研究科地域連携センター・研究員)
対立回避の事例報告:イリンガ州ンジョンベ県
10月30日(日)
9:00 加藤太(信州大学農学部・研究員) 牧民と農耕民の対立と共生―タンザニア・キロンベロ谷の事例
10:00 田村賢治(地域計画連合 国際グループ・シニアプランナー) タンザニアにおける水田稲作と水争いの現状
11:00 総合討論
12:00 掛谷誠(京都大学・名誉教授) 総括
[政治・国際関係ユニット第1回研究会]佐々木和之「地域共同体裁判『ガチャチャ』は和解の促進に貢献したのか?」(2011年10月28日開催)
日 時:2011年10月28日 (金) 10:30~12:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階小会議室1
プログラム
題目:「地域共同体裁判『ガチャチャ』は和解の促進に貢献したのか? 」
講演者:佐々木和之氏(Faculty of Development Studies, Protestant Institute of Arts and Social Sciences (PIASS))
報告
ルワンダにおいて、ガチャチャは国家が定めた法に基づく刑事裁判でありながらも、慣習的な紛争解決規範に基づき、加害者による謝罪や賠償を重視するなど、地域共同体レベルの和解を志向して実施されたことから、移行期正義の修復的アプローチとして注目されてきた。審理件数は120万件を超え、その活動を終えつつあり、現在その終結宣言が待たれている最終段階にあるが、その裁判記録の修正などで終結宣言の見通しが不透明である。本研究会において、佐々木氏は、修復的正義と応報的正義の関係性、ガチャチャの概要に関しての紹介を行った後で、制度設計上有していた修復的特徴について説明を行った。さらに、ガチャチャに対する様々な批判(適正な法手続の不備、「勝者の裁き」)を踏まえ、制度設計上試みられた修復的特徴が生かされたのかに関する評価が示された。フトゥの消極的なコミットメント、加害者の自白の信憑性、公益奉仕刑が公共事業向け労働力のプールとなっている点、そして国家補償の不履行といった観点から、制度が意図していたと考えられる修復的成果をあげることができなかったというのが、主な結論である。そして、この理由としては、これまでの批判としてもあげられてきた「勝者の裁き」とも通底するが、「正義と和解」という取り組み自体が、現在のルワンダにおいてきわめて政治化されているという背景が関わっており、そもそもその制度設計を含め、こうした取り組みが「誰のために」なされているかに関する問題が付随しているためである、という点が改めて確認された。
今回の報告に対して、出席者からは従来のガチャチャとの差異や、今回のガチャチャがこれまでのガチャチャのあり方に及ぼした影響などに関する質問が出された。さらには、今回の取り組みが「記録」され、将来世代に影響を及ぼしうるのかというアーカイブ化と、その記録が持ちうる政治性などに関わる論点も提起された。さらには、今回のガチャチャの取り組みが修復的正義の実現と成功しなかったとしても、今後これを触媒とした新たな取り組みがあり得るかといった論点も提起された。このほかにも、佐々木氏の現地における調査に関するこれまでの経緯などについての質問も出され、活発な議論が行われ、予定を30分以上超過し、盛況のうちに閉会した。(遠藤貢)

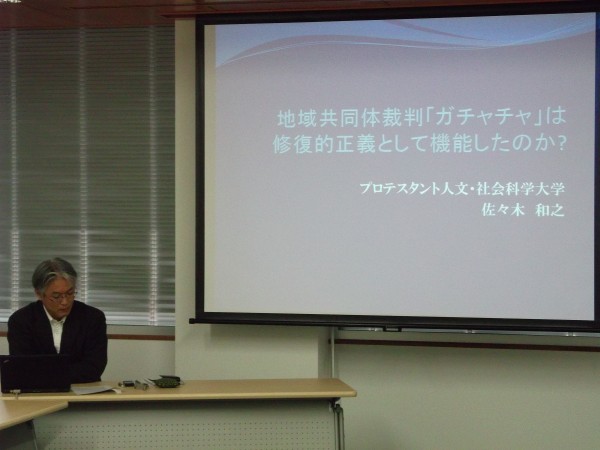
[社会・文化ユニット第3回研究会/第3回公開ワークショップ]「現代アフリカにおける先住民と市民社会」(第2回Kyoto University African Studies Seminarとの共催、2011年10月21日開催)
「現代アフリカにおける先住民と市民社会」
京都大学アフリカ地域研究資料センター
第2回Kyoto University African Studies Seminar
日 時: 2011年10月21日(金)15:00-18:00
場 所: 京都大学稲盛財団記念館小会議室2 (http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/about/access.html)
共催:京都大学アフリカ地域研究資料センター
プログラム
15:00-15:10 趣旨説明
15:10-16:30 ジョン・ギャラティ(マッギル大学) 「マサイにおける土地紛争と市民社会―ローカルな闘争とグローバルな聴衆」
16:30-16:40 休憩
16:40-18:00 丸山淳子(津田塾大学) 「再定住、開発、先住民運動―南部アフリカ、サン・コミュニティの二つの事例から」
Date: 15:00-18:00 21 Oct 2011
Venue: Small Seminar Room, 3F Inamori Bldg., Kawabata Campus http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/en/about/access.html
15:00-15:10 Introduction
15:10-16:30 John Galaty (McGill University) “Maasai Land Conflicts and Civil Society: Local Struggles and a Global Audience”
16:30-16:40 Coffee break
16:40-18:00 Junko Maruyama (Tsuda College) “Resettlement, Development and Indigenous Peoples’ Movement: Two Cases from San Communities in Southern Africa”
発表要旨
John Galaty “Maasai Land Conflicts and Civil Society: Local Struggles and a Global Audience”
The ascendency of the state in Africa and the process of privatizing agrarian land has made many rangeland communities vulnerable to having their mobility drastically curtailed and even to losing their land. This paper will examine the opportunistic seizure of pastoral lands by a variety of actors, including smallholder farmers, political class, entrepreneurs, commercial farmers, speculators, conservationists, tour operators, miners, and foreign states, from the colonial period to the present. From small- to large-scale, valuable pastoral lands have been or are being acquired through local incursions, state allocation or purchase, promising to use it for highly efficient commercial agriculture, or by conservation groups and entrepreneurs who vow to protect wildlife and at the same time propagate high-end lucrative tourist ventures. Land displacements have come to represent a major cause of violent conflicts and legal disputes in pastoral regions. In recent decades, organizations of civil society have increasingly sprung up to defend pastoral land rights, often linking their causes to claims of indigeneity anchored in the creation of the Permanent Forum on Indigenous Issues. The global audience for indigenous land loss and the advocacy of national and international civil society has both mitigated and stimulated local conflicts. Paradoxically, as indigenous land rights have been recognized, actual land loss has accelerated due to the increasingly aggressive role of the state in large-scale land acquisitions by outside parties. This paper will examine the interaction between land grabbing, land losses, and land conflicts, and role played by civil society and assertions of indigenous rights in Eastern and Southern Africa, with special focus on the experience of the Maasai of Kenya and Tanzania.
Junko Maruyama “Resettlement, Development and Indigenous Peoples’ Movement: Two Cases from San Communities in Southern Africa”
The notion that indigenous peoples should have the right to maintain their distinct cultures, lifestyles, and territories has become widely accepted within the international community during the last two decades. While the concept “indigenous peoples” is highly controversial in African context compared with the more consensual situation in nations with white settlers, the San hunter gatherers of Southern Africa also have been involved in global indigenous peoples’ movement, and become one of the best-known “indigenous peoples” in Africa. Indeed, recently some groups of the San have successfully acquired land rights, with the support of the global movement. Of these, two cases from Botswana and South Africa will be highlighted in this presentation; Botswana San won in court the right to return to their land in nature conservation area, and the San in South Africa were handed over land title deeds from President Mandela. Both cases were hailed by NGOs, activists, and the mass media as a landmark for the rights of indigenous peoples in Africa. This presentation will analyze the historical backgrounds and the negotiation process of these two cases, and then elucidate the San’s livelihood and social relationships after they gained land-use rights. Finally, by comparing both cases, dynamics underlying relationships between the San and national and international communities, and positive and negative impacts of the global indigenous peoples’ movement on the San will be discussed.
報告
ジョン・ギャラティ(マッギル大学) 「マサイにおける土地紛争と市民社会―ローカルな闘争とグローバルな聴衆」
ギャラティ氏は、東アフリカ牧畜社会で進展している開発プロジェクトに関する発表をおこなった。とくに多様なアクターを巻き込みながら展開している、牧畜民が利用している土地の剥奪について中心的に論じた。それらの土地は、大規模商業農場や野生動物保護区にすることなどを目的として、国家や外国・国内企業などが取得している。またより小規模ではあるが、農耕民による放牧地の農地化も進められてきた。この土地剥奪は牧畜集団間の土地をめぐる相克を深める危険がつよいが、近年では市民社会組織らが「土着性(indigeneity)」の主張を武器に、牧畜民の土地権利を保護するための活動をおこなっている。これらの組織の活動は、ローカルな紛争を緩和することがある一方で、新たな対立軸を地域に持ち込むことで、紛争をより複雑なものにすることもある。そして皮肉なことに、グローバルな市民社会組織の権利保護活動が高まりつつある時期に、国家は外国資本などによる大規模な土地取得を擁護する政策を取っているのである。
丸山淳子(津田塾大学) 「再定住、開発、先住民運動―南部アフリカ、サン・コミュニティの二つの事例から」
アフリカでは、アメリカ大陸やオーストラリアとは異なり、「先住民」という概念はきわめて論争的な概念である。丸山氏は、アフリカの「先住民」としてもっともよく知られた集団の一つであるサンの人びととグローバルな先住民運動とのかかわりを、ボツワナと南アフリカの事例から比較検討した。サンは近年になって、グローバルな先住民運動からの支援を受けつつ、土地への権利を取得することに成功した。ボツワナでは、司法判断により自然保護地域とされていた彼らのもともとのテリトリーが返還されることになり、南アフリカではマンデラ大統領による土地権利譲渡によって土地を獲得した。丸山氏は、両地域の土地取得にいたるまでの歴史的背景やローカル、ナショナル、グローバルなアクターを巻き込んだ先住性をめぐる交渉プロセス、そして土地取得後のサンの人たちの生活戦略を分析したあと、グローバルな先住民運動がサンにもたらしたポジティヴ、ネガティヴな側面をまとめた。
[第3回公開ワークショップ/社会・文化ユニット第3回研究会]「現代アフリカにおける先住民と市民社会」(第2回Kyoto University African Studies Seminarとの共催、2011年10月21日開催)
「現代アフリカにおける先住民と市民社会」
京都大学アフリカ地域研究資料センター
第2回Kyoto University African Studies Seminar
日 時: 2011年10月21日(金)15:00-18:00
場 所: 京都大学稲盛財団記念館小会議室2 (http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/about/access.html)
共催:京都大学アフリカ地域研究資料センター
プログラム
15:00-15:10 趣旨説明
15:10-16:30 ジョン・ギャラティ(マッギル大学) 「マサイにおける土地紛争と市民社会―ローカルな闘争とグローバルな聴衆」
16:30-16:40 休憩
16:40-18:00 丸山淳子(津田塾大学) 「再定住、開発、先住民運動―南部アフリカ、サン・コミュニティの二つの事例から」
Date: 15:00-18:00 21 Oct 2011
Venue: Small Seminar Room, 3F Inamori Bldg., Kawabata Campus http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/en/about/access.html
15:00-15:10 Introduction
15:10-16:30 John Galaty (McGill University) “Maasai Land Conflicts and Civil Society: Local Struggles and a Global Audience”
16:30-16:40 Coffee break
16:40-18:00 Junko Maruyama (Tsuda College) “Resettlement, Development and Indigenous Peoples’ Movement: Two Cases from San Communities in Southern Africa”
発表要旨
John Galaty “Maasai Land Conflicts and Civil Society: Local Struggles and a Global Audience”
The ascendency of the state in Africa and the process of privatizing agrarian land has made many rangeland communities vulnerable to having their mobility drastically curtailed and even to losing their land. This paper will examine the opportunistic seizure of pastoral lands by a variety of actors, including smallholder farmers, political class, entrepreneurs, commercial farmers, speculators, conservationists, tour operators, miners, and foreign states, from the colonial period to the present. From small- to large-scale, valuable pastoral lands have been or are being acquired through local incursions, state allocation or purchase, promising to use it for highly efficient commercial agriculture, or by conservation groups and entrepreneurs who vow to protect wildlife and at the same time propagate high-end lucrative tourist ventures. Land displacements have come to represent a major cause of violent conflicts and legal disputes in pastoral regions. In recent decades, organizations of civil society have increasingly sprung up to defend pastoral land rights, often linking their causes to claims of indigeneity anchored in the creation of the Permanent Forum on Indigenous Issues. The global audience for indigenous land loss and the advocacy of national and international civil society has both mitigated and stimulated local conflicts. Paradoxically, as indigenous land rights have been recognized, actual land loss has accelerated due to the increasingly aggressive role of the state in large-scale land acquisitions by outside parties. This paper will examine the interaction between land grabbing, land losses, and land conflicts, and role played by civil society and assertions of indigenous rights in Eastern and Southern Africa, with special focus on the experience of the Maasai of Kenya and Tanzania.
Junko Maruyama “Resettlement, Development and Indigenous Peoples’ Movement: Two Cases from San Communities in Southern Africa”
The notion that indigenous peoples should have the right to maintain their distinct cultures, lifestyles, and territories has become widely accepted within the international community during the last two decades. While the concept “indigenous peoples” is highly controversial in African context compared with the more consensual situation in nations with white settlers, the San hunter gatherers of Southern Africa also have been involved in global indigenous peoples’ movement, and become one of the best-known “indigenous peoples” in Africa. Indeed, recently some groups of the San have successfully acquired land rights, with the support of the global movement. Of these, two cases from Botswana and South Africa will be highlighted in this presentation; Botswana San won in court the right to return to their land in nature conservation area, and the San in South Africa were handed over land title deeds from President Mandela. Both cases were hailed by NGOs, activists, and the mass media as a landmark for the rights of indigenous peoples in Africa. This presentation will analyze the historical backgrounds and the negotiation process of these two cases, and then elucidate the San’s livelihood and social relationships after they gained land-use rights. Finally, by comparing both cases, dynamics underlying relationships between the San and national and international communities, and positive and negative impacts of the global indigenous peoples’ movement on the San will be discussed.
報告
ジョン・ギャラティ(マッギル大学) 「マサイにおける土地紛争と市民社会―ローカルな闘争とグローバルな聴衆」
ギャラティ氏は、東アフリカ牧畜社会で進展している開発プロジェクトに関する発表をおこなった。とくに多様なアクターを巻き込みながら展開している、牧畜民が利用している土地の剥奪について中心的に論じた。それらの土地は、大規模商業農場や野生動物保護区にすることなどを目的として、国家や外国・国内企業などが取得している。またより小規模ではあるが、農耕民による放牧地の農地化も進められてきた。この土地剥奪は牧畜集団間の土地をめぐる相克を深める危険がつよいが、近年では市民社会組織らが「土着性(indigeneity)」の主張を武器に、牧畜民の土地権利を保護するための活動をおこなっている。これらの組織の活動は、ローカルな紛争を緩和することがある一方で、新たな対立軸を地域に持ち込むことで、紛争をより複雑なものにすることもある。そして皮肉なことに、グローバルな市民社会組織の権利保護活動が高まりつつある時期に、国家は外国資本などによる大規模な土地取得を擁護する政策を取っているのである。
丸山淳子(津田塾大学) 「再定住、開発、先住民運動―南部アフリカ、サン・コミュニティの二つの事例から」
アフリカでは、アメリカ大陸やオーストラリアとは異なり、「先住民」という概念はきわめて論争的な概念である。丸山氏は、アフリカの「先住民」としてもっともよく知られた集団の一つであるサンの人びととグローバルな先住民運動とのかかわりを、ボツワナと南アフリカの事例から比較検討した。サンは近年になって、グローバルな先住民運動からの支援を受けつつ、土地への権利を取得することに成功した。ボツワナでは、司法判断により自然保護地域とされていた彼らのもともとのテリトリーが返還されることになり、南アフリカではマンデラ大統領による土地権利譲渡によって土地を獲得した。丸山氏は、両地域の土地取得にいたるまでの歴史的背景やローカル、ナショナル、グローバルなアクターを巻き込んだ先住性をめぐる交渉プロセス、そして土地取得後のサンの人たちの生活戦略を分析したあと、グローバルな先住民運動がサンにもたらしたポジティヴ、ネガティヴな側面をまとめた。
[社会・文化ユニット第2回研究会](2011年09月23日開催)
日 時:2011年9月23日 (金)
場 所:京都大学稲盛記財団記念館3階小会議室1
プログラム
15:00~18:00:構成メンバーの研究紹介
松田素二 ケニアPEVに対するローカルイニシャティブの可能性
太田至 トゥルカナの人々の対面的交渉力と秩序形成:難民キャンプとのつきあいのなかで
平野美佐 家族の「紛争」とその解決:カメルーンのやもめ儀礼
近藤英俊 ナイジェリア北部の慢性化する紛争
内藤直樹 社会の「外部」に生きる:ケニア・ダダーブ難民キャンプ複合体における長期化難民の生活実践
佐川徹 大規模土地取引がエチオピアの地域社会に与える影響
梶茂樹 紛争予防機能としてのマルチリンガリズムの可能性
報告
今回は、各構成メンバーが本科研において焦点を当てようとしている研究課題の概要について発表をおこなった。松田氏は、ケニアでの2007年~2008年の選挙後暴力(PEV)時に、ナイロビのスラムに暮らす人びとが地域の治安を確保するために、自発的にコミュニティーポリシング活動を開始した経緯を紹介した。太田氏は、ケニア北部のトゥルカナの人びとが、彼らの居住地域につくられた難民キャンプに暮らす難民とのあいだに個人的な友好関係を形成したり、家畜商人集団を組織して家畜泥棒に備えている事例を示した。平野氏は、カメルーンのバミレケ社会では、夫が死亡した際に「夫を殺したという疑い」を晴らすためにおこなうやもめ儀礼を取り上げ、儀礼ではほとんどの場合妻は「無実」になることを論じ、この儀礼が寡婦となった女性を社会に再統合させる役割を担っていることを論じた。近藤氏は紛争多発地域であるナイジェリア北部で1960年代以降発生してきた大規模な紛争についてまとめ、今後どのような形で地域の対立構造が緩和しうるのかを考察していくことを述べた。内藤氏は、ケニアのダダーブ難民キャンプにおいて、長期化する難民状態はホスト国や難民キャンプ周辺に住む人々にとっても日常化しつつあり、難民と地域住民との長期にわたる相互交渉の結果、地域に新しい「日常生活」が作り上げられつつある点を指摘した。佐川氏は、エチオピアでは政府が海外直接投資を積極的に受け入れ、大規模な土地をリースで外部資本に貸し出していることを指摘し、今後、地域住民とそれらの外部勢力との間に紛争が生じる可能性について触れた。梶氏は、ウガンダの地方都市での社会言語学的調査の結果から、多くの人びとがマルチリンガルであることが紛争の予防といかなる関係を有しているのかを検討していきたいと述べた。
最後に松田氏が、過去に各地域社会で機能していた紛争解決方法はどのようなものであったのか、それらがどのように歴史的に変化してきたのか、それらは現在いかなる紛争解決機能を担っているのか、あるいはいないのか、を検討することが、「社会・文化ユニット」で今後検討されるべき基本的な課題であると述べた。(伊藤義将、佐川徹)
[第2回全体会議]「ケニアにおける2007年末の総選挙をめぐる暴力事件の実態とその後の和解プロセス」(2011年09月23日開催)
日 時:2011年9月23日(金)
場 所:京都大学稲盛記財団記念館3階中会議室
プログラム
11:00~12:00 津田みわ(アジア経済研究所) 「調停から国際刑事裁判所へ:ケニア2007/8年紛争への取り組み」
12:00~12:30 松田素二(京都大学) 「ケニア真実正義和解委員会方式の現状と問題」
12:30~13:00 内藤直樹(国立民族学博物館) 「総選挙にともなう集団間の対立とそのローカルな解決:北ケニア牧畜民アリアールの事例」
13:00~14:30 全体討論
報告の概要
第2回全体会合では、2007年から2008年にかけてケニアで発生した選挙後暴力(Post-Election Violence: PEV)とその後の紛争処理過程に焦点を当てた発表を3名がおこなった。津田みわ氏は、PEVが発現するにいたった背景と暴力がもたらした被害についてまとめたあと、紛争後のケニア国内での調停プロセスが頓挫し、国際刑事裁判所(ICC)に事態が委ねられていった過程を説明した。2008年10月に出されたワキ委員会の報告書では、国内にPEVに関する特別法廷を設置することが勧告されたものの、国会での多数派工作が進まず法廷の設置はできなかった。そこで2009年10月に、キバキ大統領とオデンィガ首相は、ワキ委員会が同定しリスト化していたPEVに責任のある容疑者の裁きをICCに委ねる意向を表明した。2010年12月にICCは、PEVの際に「人道に対する犯罪」2件がおこなわれたとして、容疑者6人の名前を公表し、2011年3月に6人への召喚状を発行した。現在、ICCでは予審裁判部で審理がおこなわれており、「被疑者が各犯罪を行ったと信ずるに足りる充分な証拠が、存在するか否か」が議論されている。質疑では、ICCについて国内で支持しているのは都市の知識人がおもであり、むしろ召喚状が出された6人は、多くの国民から「欧米植民地勢力の犠牲となった殉教者」のような扱いを受けていることなどが論じられた。
つぎに松田素二氏は、ケニアでの真実正義和解委員会の設置にいたるプロセスと現状を説明した。委員会は2008年4月に制定された「国民調和と和解法」にもとづいて2009年8月に活動を開始したが、実質的には放置されていた。2011年4月になってようやく国内各地での公聴会を開始した。委員会の活動では、アパルトヘイト廃止後の南アフリカで設置された真実和解委員会が採用した対話型真実を重視した和解が模索されている。委員会に対しては、責任者の処罰を求める「ワキ報告書」の実行を遅らせるための政治的道具としてそれが用いられてしまう可能性がある点、独立以来、ケニア政治の中枢にあり続けた現職大統領に真実委員会を設置する正統性がない点、対象期間が1963年の独立以後の時期にかぎられており、それ以前になされた英国植民地政府による重篤な人権侵害が検討課題から除外されている点、などに対して批判もなされている。質疑では、委員会に対して一般国民がどのような評価や期待をしているのかが論じられ、国民の期待はほとんどなく、またニュースで取り上げられることもまれであり、新聞に記事が掲載されたとしても、ICC関連のそれが政治欄に載るのに対して、委員会のそれは読み物の紙面に載せられているという。また、ケニアに限らず真実委員会のような試みに西側諸国などが期待を抱くのに対して、当該国の一般市民からはあまり大きな注目を集めないのはなぜか、という問いも出された。
三人目の発表者である内藤直樹氏は、北ケニアのアリアール社会で、2006年と2007年の国会議員選挙を契機に近隣集団との間につよい敵意が創出されたあと、それが選挙後にいかに解消されていったのかを明らかにした。ケニアでは、2003年に選挙区開発基金が導入されて、各選挙区に国会議員が「自由に」使える資金が配分されるようになったことで、地域住民の選挙への関心が高まった。アリアール社会でも、同一の選挙区を構成しアリアールがそれまで「兄弟」として認識していたレンディーレの人びとが、選挙期間中に立候補者によって「敵」として同定され、集団間に亀裂が深まった。しかし選挙後には、人びとは選挙時に創出・強化された差異について語るのではなく、むしろそれを語らずに差異を隠ぺいすることをとおしてこれ以上の関係の悪化を防ごうとしている。この人びとの「語らない」という姿勢が、対立の激化を防ぐ機能を果たしていることを、内藤氏は強調した。質疑では、選挙以前の「日常」と、選挙で集団間の敵意が強化されたあとに復帰した「日常」とのあいだで、人びとの社会関係に不可逆的な変化が生じたのか否か、といった問いが出された。
全体討論の場では、最初に、ケニアのPEVを処理する際にICCのような「法による厳正な処罰」を求める立場と、より「アフリカ的」な紛争処理を求める立場との関係をどのように捉えればいいのかに関する議論が展開した。 まず、ICCが試みている「法による厳正な処罰」を求める動きに対して、ケニア国内でも批判がなされているが、その批判勢力の一部を構成しているのは政治的不処罰(political impunity)の存続を求める政治家などであり、人類学の立場からなされる「西洋社会が押し付ける普遍的正義によってではなく、アフリカの潜在力を用いて事態を解決する道を模索すべきだ」という主張は、慎重におこなわないとそのような立場と同一視されてしまう危険性が高いことが指摘された。
また、「アフリカに任せても不処罰に向かうだけだからICCが法に則ってグローバル・スタンダードで裁けばいい」という、国際社会で主張されている議論に関する考えを各人が示し、「悪いことをした人はなんらかの形で裁かれなければならない」というのが大原則として事を進められるべきである、国内での特別法廷の設置に失敗した結果としてICCに委ねられたのだからその責任はケニア政府が負う必要がある、不処罰は「やり逃げ」を長期的に再生産する可能性がつよいが、それを処罰するために外部機関が関与し、たとえば当該国にナショナリズムを喚起することの長期的インパクトも同時に考える必要がある、国際司法の側も単に地域的文脈を無視して普遍的正義を主張しているのではなく活動を重ねるごとに当該国の世論形成にも配慮しつつある、「法による処罰」を推進する権化のように映るICCであっても、容疑者を決定する過程などでは法のみに依拠して意思決定がなされているのではなく、法外の要因もつよく考慮している、といった点が論じられた。
さらに、ICCの介入に対して、アフリカの人びとが過剰にリアクションしないところに、「アフリカ的」な反応を見て取ることができるとの指摘もなされた。くわえて、紛争後処理において、ICC、国家、ローカルなコミュニティがそれぞれどのような犯罪行為を取り扱うことになるのかは、西側諸国を中心とした国際社会が設けた基準におもに依拠してなされているが、アフリカの多くの社会では「犯罪者」に対する懲罰が一般的に希薄であり、その観点から「重篤犯罪」とそれ以外の問題行為との境界線をずらしていく作業を進めていくことの必要性も論じられた。
つぎにケニアの事例にかぎらず、より一般的にアフリカの潜在力が、大規模な組織的暴力をともなう紛争の抑止や紛争後の対立勢力間の和解に、いかなる効力を有しているのか、あるいは有していないのか、に焦点を当てた議論がなされた。まず、アフリカの潜在力は現在にいたるまで軽視され続けてきたため、それを紛争の抑止や処理に適切に活用していく方途を考えていくことは必要だが、同時にそのような潜在力が機能しない局面も存在することを認識し、それを活用して解決が可能な問題とそうでない問題のちがいについて考察していく必要がある、との指摘がなされた。これと関連して、紛争が激化していく過程には、引き返すことができない地点(point of no return)が存在しており(たとえばルワンダでは1959年の「社会革命」時の暴力)、一度その地点を越えると、より大規模な組織的暴力をともなう紛争の発生を抑止することがきわめて難しくなってしまうが、逆にいえばその地点を越えてしまうまえに、潜在力を活用して、「後戻り」する可能性が残されていることも論じられた。最後に、アフリカの諸社会は、紛争がより頻繁に起きる可能性を内包し続けてきたにもかかわらず、紛争が発現するまえの段階で比較的うまくそれを抑止しえてきた社会であると特徴づけることもでき、その抑止の具体的なあり方を明らかにしていくことの必要性が指摘された。(佐川徹)
[社会・文化ユニット第1回研究会]「Peace, Violence and Cross-Cutting Ties among African Pastoral Societies」(2011年07月29日開催)
日 時:2011年7月29日 (金) 13:40~17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階 318号室
主 催:京都大学アフリカ地域研究資料センター
プログラム
13:40-14:00 Introduction Itaru Ohta (Kyoto University)
14:00-15:00 “Bad Friends and Good Enemies: Constructions of Peace and Violence in the Samburu-Pokot-Turkana Triad (Northern Kenya)” Jon D. Holtzman (Western Michigan University)
15:00-15:15 Break
15:15-16:15 “The Role of Cross-Cutting Ties in the Cameroon Grassfields” Michaela Pelican (University of Zurich)
16:15-16:30 Break
16:30-17:30 Discussion Motoji Matsuda (Kyoto University)
報告
「趣旨説明」
太田至(京都大学)
1990年代以降、アフリカでは一般市民を巻き込んだ紛争が頻発した。現在、これらの紛争で生じた社会的混乱をいかに解決するのかが紛争を経験したアフリカ社会の大きな課題となっている。これまでに、国際社会が国際刑事裁判所やPKOを通じて、またNPOやNGOが市民社会を先導するようなかたちで、紛争を経験した社会の再生を試みる活動が行なわれきた。しかし、そのような活動から得られた効果は限定的であった。
本プロジェクトでは、アフリカ人がみずから創造・蓄積し、運用してきた知識や制度(=潜在力)を解明し、それを紛争解決と社会秩序の構築(=共生)のために有効に活用する道を探究することを目的とする。
“Bad Friends and Good Enemies: Constructions of Peace and Violence in the Samburu-Pokot-Turkana Triad”
Jon Holtzman (Western Michigan University)
ケニア北部に住む牧畜民、サンブルとポコットは1850年代に当時激化しつつあった紛争を儀礼の執行をとおして沈静化させた。その儀礼では、両者が互いの成員を殺し合わないことを誓い、2つの民族間には和平がもたらされた。その誓約は2006年に紛争が勃発すると破約した。しかし、2006年以前からサンブルとポコットの間に協力関係が見られることは稀であり、また通婚の事例も少なかったことから、彼らが本当の意味で友好関係を形成していたとは言い難い。サンブルとポコットの間で保たれた和平は友愛によって成立したわけではなく、儀礼に従うかたちで達成されたものであった。そのため、2つの民族間に武力紛争こそ生じることはなかったものの、感情的には互いに嫌悪感を募らせるというねじれた関係が生み出されたのである。 一方で、サンブルはトゥルカナと常に紛争状態にある。しかし、サンブルとトゥルカナとの間には協力的な関係や通婚の事例が多く見られたり、多くのトゥルカナがサンブルと一緒に生活しているという事例が見られたりする。すなわち、サンブルとトゥルカナの間に紛争が絶えることはないものの、2つの民族の関係は親密なものであることが伺える。このことから、親密な関係があるからこそ、2つの民族の間には紛争が絶えないとも考えられる。
このような事例は現地の潜在力を生かして達成された和平と国際社会などの外部圧力によってもたらされた和平を理解する際に役立つであろう。また、この事例から強制的に争いを沈めることと、和平をもたらすことは異なるものであり、平和と紛争は必ずしも対立する概念ではないことを伺い知ることができる。
“The Role of Cross-Cutting Ties in the Cameroon Grassfields”
Michaela Pelican (University of Zurich)
横断的紐帯(Cross-cutting ties)とは1960年代にMax Gluckmanによって生み出された概念で、複数の民族、文化、社会を横断するような関係である。そして、このような関係は複数の民族間の通婚を促進し、友好的な関係をもたらしていると言われてきた。カメルーン北部のGrassfields peoplesと呼ばれる人々とボロロやハウサの関係を見ると、確かに横断的紐帯は複数の民族のかかわりを密接なものにし、民族間の対話を促す役割があると考えられる。しかし、紛争が勃発し、それが激化するとともに、通婚などによって複数の民族に帰属意識を持つ人々は、それぞれの民族からの批判や嫌がらせに晒されることになる。カメルーン北部の事例を見る限り、横断的紐帯の多少と紛争の強度や頻度との間に相関関係を見出すことはできない。横断的紐帯は紛争後の平和構築と複数民族の共生にある程度寄与することが外部セクターによって期待されてきたが、カメルーンの事例では、紛争の勃発により横断的紐帯は切断され、紛争後には、対立しあった民族の成員は互いに接触を断つ忌避戦略(avoidance strategy)を選択する傾向にある。
「質疑応答」
質疑応答では、牧畜民の社会には日常生活に埋め込まれたような紛争が存在するため、このプロジェクトで取り扱う「紛争」を定義しなければ、何をもって紛争解決となるのか混乱を招くという点が話しあわれた。また忌避戦略のように、親密な関係を回避するような行為は、異なる民族間に誤解を生じさせ、紛争を更に激化させる可能性がある点が確認された。(伊藤義将)
[第2回公開ワークショップ]荒木茂「サイエンスと地域研究の狭間で―実践的地域研究の試み」(第181回アフリカ地域研究会との共催、2011年7月21日開催)
日 時:2011年7月21日(木)15:00 ~ 17:00
場 所:京都大学稲盛財団記念館3階中会議室
題 目:サイエンスと地域研究の狭間で-実践的地域研究の試み
発表者:荒木 茂(京都大学アフリカ地域研究資料センター・教授)
要 旨:サイエンスが世の中にどれだけ役に立ってきたか、ということに対する疑問は多く挙げられてきた。福島原発事故がそれを加速することは必至である。しかし、地域研究が文理融合、学際的アプローチによって(個別科学を具体的場面に役立てる手段として)サイエンスを飼い慣らすことができれば、実践的地域研究として復権する可能性を秘めている。本発表は、開発に関わる科学者の仮説と、現地の人々の実践が邂逅する点をさぐるプロセスを、「不確実性の科学」として定置する試みを、カメルーンにおけるJST/JICA「森林-サバンナ持続性プロジェクト」を例に紹介したい。
[第1回 全体会議/第1回公開講演会]「アフリカの紛争と共生:キックオフ」(2011年07月02日開催)
日時:2011年7月2日 (土) 13:30~16:00
場所:京都大学稲盛財団記念館3階大会議室
共同主催:京都大学アフリカ地域研究資料センター
事前申し込:不要 Flyer(PDF)
内容
現代のアフリカ社会が直面する最大の困難は、紛争による社会秩序の解体と疲弊です。アフリカでは、とくに1990年代に入ってから大規模な内戦や地域紛争が頻発し、また、土地の所有と利用をめぐる暴力的衝突や政治資源をめぐる地域的な争いなど、多種多様な紛争が起こっています。そして国際社会は、リベラル・デモクラシーなどの欧米出自の思想や価値規範にもとづいて、こうした事態の解決をめざしてきました。 これに対して本ワークショップでは、まったく異なる立場をとります。それは、紛争解決や共生の実現のためにアフリカ人がみずから創造・蓄積し、運用してきた知識や制度があるという視点です。ただし、そうした知識や制度はアフリカに固有で変わらない実体ではなく、外部世界とのあいだで衝突や接合を繰り返しながら生成されたものです。本ワークショップではこうした知識や制度を、現在の紛争処理や社会修復のために活用する道を考えます。
キーワード
ルワンダ, 平和構築, 南スーダン共和国, ポストコンフリクト, 国家建設
プログラム
13:30~13:45 趣旨説明:太田 至(京都大学)
13:45~14:45 栗本英世(大阪大学)「回復しないコミュニティレベルの平和 ―「戦後」南部スーダンにおける平和構築の課題と限界―」
14:45~15:00 休憩
15:00~16:00 武内進一(JICA研究所)「紛争後ルワンダの国家建設とガチャチャ」
報告の概要
「趣旨説明」 太田至(京都大学)
本ワークショップは、2011年度から5年間の予定で実施する研究プロジェクト「アフリカの潜在力を活用した紛争解決と共生の実現に関する総合的地域研究」(科学研究費補助金・基盤研究(S))のスタートを記念するものである。現代のアフリカ社会は、紛争による社会秩序の解体と疲弊という大きな困難に直面している。この現実的課題に対して本プロジェクトは、西欧近代の制度や価値観を導入して対処するのではなく、アフリカ人がみずから創造・蓄積し、運用してきた知識や制度(=潜在力)を解明し、それを紛争解決と社会秩序の構築(=共生)のために有効に活用する道を探究することを目的とする。(太田至)
「回復しないコミュニティレベルの平和―「戦後」南部スーダンにおける平和構築の課題と限界―」 栗本英世(大阪大学)
Unrestored Peace at the Community Level: Challenges and Limits of the Peace-Building in the “Post-War” Southern Sudan Eisei Kurimoto (Osaka University) 2011年7月に独立が予定されている南スーダンでは、2005年の包括的平和合意の調印後、スーダン政府軍とスーダン人民解放軍(SPLA)の間には平和がおおむね保たれている。しかし、コミュニティレベルの平和は十分に達成されておらず、異なるコミュニティ間だけでなく同一のコミュニティ内でも武力紛争が発生している。コミュニティレベルの和解の促進を目的とした平和会議が開催されている地域もあるが、十分な成果は上げておらず、そのような試みすらなされていない地域もある。地域社会を再構築していくためには、コミュニティに内在する平和への意志(「平和力」)に注目した「下からの平和」のアプローチが重要であるとともに、「下からの平和」の動きを政府らが実施する「上からの平和」の営みと有機的に接合していく必要がある。 質疑応答の時間には、「下からの平和の営みを支援するためには具体的にどうすればいいのか」、「下からの平和と上からの平和の営みをだれがどう接合するのか」、「平和会合の開催だけでなく、より個人レベルでなされる商業活動を活性化していくことが必要ではないか」といった質問をもとに議論がなされた。(佐川徹)
「紛争後ルワンダの国家建設とガチャチャ」 武内進一(JICA研究所)
Rwanda’s Gacaca under the Post-Genocide State Building Shinichi TAKEUCHI (JICA Research Institute) 紛争後の国家建設と平和構築を、「政治的安定(Political sustainability)」と「異議・アカウンタビリティ(voice and accountability)」の指標から判別すると、三類型に類別できる。その類型とは、(1)両者の指標が低位のタイプ(例 アフガニスタン、スーダン)、(2)「政治的安定」の改善が「異議・アカウンタビリティ」指標の改善より大きいタイプ(例 ルワンダ、アンゴラ)、(3)「政治的安定」と「異議・アカウンタビリティ」の両方が改善したタイプ(例 ブルンジ、リベリア)である。紛争後の国家建設の実態は、国際社会の想定とはギャップがあり、紛争当事者の一方が政権を握ると強権化し、レジティマシーが失われる可能性が高くなることが指摘された。1990年~1994年にかけて内戦とジェノサイドを経験したルワンダでは、RPF(ルワンダ愛国戦線)が紛争後の国家建設を進めてきた。そのなかで、ジェノサイドに荷担した人物を裁く裁判、ガチャチャがおこなわれ、そのなかでは自白による刑期の半減が認められた。ガチャチャという裁判制度が始まり、トゥチは家族を殺害した犯人の検挙、真相の解明を期待する一方で、フトゥは家族の冤罪を晴らし、釈放を期待していた。ガチャチャの判決は、ひどくゆがんだものではないが、RPFの戦争犯罪は扱われず、「勝者の裁き」となっている傾向にあるため、人々に不満と諦念を抱かせおり、「法の支配」や「民主的統治」に寄与したとはいいにくい側面がある。紛争後社会における治安維持およびレジティマシーの確立を両立させる国家建設が重要である。 質疑応答では、ルワンダとブルンジの紛争後社会のちがいについて、紛争終結の仕方、国際社会の関与の強さが強く関係することが議論された。(大山修一)
参加人数:85名