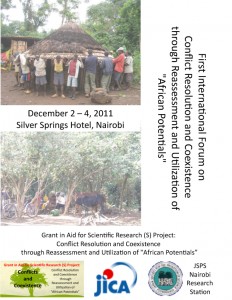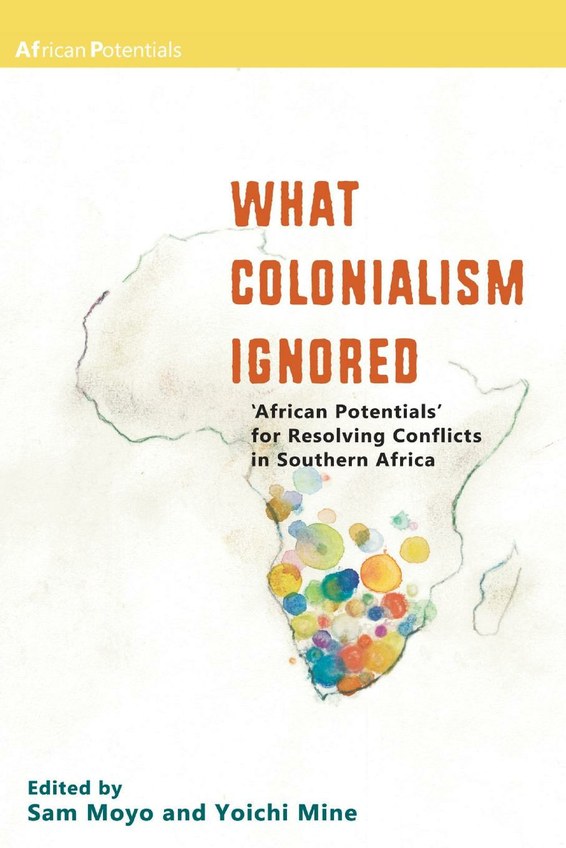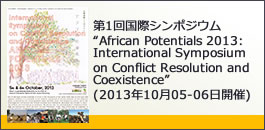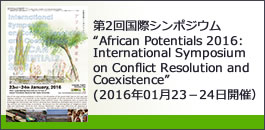[第4回全体会議]「アフリカの土地・資源をめぐるコンフリクト」(2012年01月28日開催)
日 時:2012年1月28日(土)10:00~14:30
場 所:京都大学 稲盛記念館 3階 中会議室
プログラム
10:00~10:15 事務連絡
10:15~11:15 高橋基樹・太田妃樹(神戸大学) 「所有の政治性―アフリカにおける土地問題と開発・紛争」
11:15~12:15 池野 旬(京都大学) 「政策転換・都市開発・地方公共財 ―北部タンザニア、ムワンガ県の「コモンズ」をめぐる火種」
12:15~12:45 休憩
12:45~13:45 大山修一(京都大学) 「サヘルにおける農耕民と牧畜民の土地をめぐるコンフリクト ―ローカル・ポテンシャルを活用した共生関係の再構築」
13:45~14:30 総合討論
報告
第4回全体会議では、アフリカ大陸の各地で進行中の土地をめぐる紛争と共生の問題に関して、3人(1人は共同発表)が発表をおこなった。
高橋基樹・太田妃樹(神戸大学)「所有の政治性―アフリカにおける土地問題と開発・紛争」
21世紀に入り経済成長を進めるアフリカは、いま過渡期にある。一人目の発表者である高橋基樹氏(太田妃樹氏と共同発表)は、重要なのは「どこからどこへの過度期なのか」を明確にすることであると述べる。とくに注目すべきなのは人口増加であり、2010年から2060年にかけてアフリカの人口は約2.5倍になるといわれる。これは、アフリカが土地豊富社会から土地稀少社会へ移行しつつあることを意味する。資源の稀少化は、既存の制度では調整する仕組みのない矛盾を生みだすことが多く、顕在化した対立を調整する制度的対処が必要になる。土地制度に関しては、開発経済学では、共同体的土地保有制はフリーライドを招くため、農民が土地価値を高める投資や政治的要求をする誘因を提供しないのに対して、個別的土地所有権を保障する制度を設けることで、生産性向上に資する投資や信用取引を促進すると議論されることが多い。アフリカには、1980年代の構造調整期に個別的土地所有権制度の導入が図られ、1990年代になると世界銀行内により柔軟な土地制度を容認する動きもあったが、21世紀に入ると新古典派的な土地制度論が復活した。もっとも、高橋氏が現地調査を実施したケニアの現況からは、個別的土地所有権制度の導入は排他性をともなうことで土地の稀少性をみずから生みだし、特定集団に不満を蓄積させることで政治的対立をもたらすおそれが強いことがわかる。また土地制度の形成や運用に際しては、政治家らのグリード(強欲)が深く関与していることが多い。高橋氏は、土地をめぐる紛争を予防するために、新たな土地財産権管理制度を構想することがいま求められており、その制度にアフリカの潜在的な共生の知恵をどれほど活用しうるのかを考えていく必要があると述べた。
討論では、制度の多元性と多層性、なかでも国家法と慣習法との関係をどう捉えるのかに関して議論がなされるとともに、高橋氏がいう土地問題の「暴力を排除した市民社会的な解決」とは、現在登記されている土地の所有権を尊重して事態を解決するということなのか、それとも、植民地時代から積み重ねられてきた土地をめぐる不正義の問題にまで遡って問題を打開することを意味しているのか、という質問がなされた。
池野 旬(京都大学)「政策転換・都市開発・地方公共財―北部タンザニア、ムワンガ県の「コモンズ」をめぐる火種」
二人目の発表者である池野旬氏は、タンザニアのムワンガ県における「ローカル・コモンズ」をめぐる複数の火種(調整・調停されるべき事項・争点)を紹介した。たとえば同県では、ムワンガ町の勃興にともなって新築建造物が増加し、建材への需要が高まったことで、河岸近くの土地から木や砂利が運びだされている。この土地には明確な所有権が設定されておらず、環境劣化が問題化しつつある。また、人口増加を受けて町までの水道施設が整備されたことにともない、水道公社が周辺村にも水道メーターを設置した。しかし、ある村の住民は、町が発展する以前から自分たちで水道の建設や維持管理を担ってきたという自負があり、公社からの支払い請求に反発した。村の住民は、行政や国会議員など多様なアクターとの折衝をとおして独自の水道事業を新たに開始したものの、通水時間などに関して争議が発生している。さらに、町周辺部では土地の売買が増加しており、クランが所有単位となっている土地が個人の名前で売られたり、新住民が土地を購入して流入してくることで、新たな問題が顕在化しつつある。池野氏は、武力紛争にはいたっていないが、このような多様な対立の火種が地域社会に渦巻いていることを指摘し、その対立にいかなるアクターがどのように関わっているのかを微細に検討することの重要性を述べた。また、地域住民による対処をつねに「正しい」ものとして位置付けるのではなく、研究者自身があるべき農村社会のあり方を考え、「その変容のあり方は将来的に問題を含むのではないか」という提言をすることも考えていく必要があると述べて、発表を閉じた。
討論では、土地の所有と利用の実態についてより細かな質疑がなされたとともに、池野氏が言及した村人の「環境よりまずは生活」という発言がなされた背景についての説明がなされた。また、飲料水の商品化や水道のパイプ化が地域の水資源をめぐる争いと関連を有しているのか否か、という問いも出された。
大山修一(京都大学)「サヘルにおける農耕民と牧畜民の土地をめぐるコンフリクト―ローカル・ポテンシャルを活用した共生関係の再構築」
三人目の発表者である大山修一氏は、ニジェールのサヘル地域で牧畜民と農耕民の間に発生している紛争の背景と現状を説明するとともに、日本人研究者が地域のポテンシャルを活用しながら対立関係の緩和にどう関与していくことができるのかを論じた。かつて、農耕民(おもにハウサ)と牧畜民(おもにフルベ)は農産物と畜産物を交換する経済的な共生関係を築いていた。しかし、1950年に放牧地だった土地は、現在ではほぼすべてがハウサの畑によって覆われており、牧畜民が放牧に利用できる土地は著しく減少した。その結果として今日、とくに雨季の収穫期に家畜による作物の食害が多発している。食害が起きると賠償金の交渉がなされるが、被害の実態について農耕民と牧畜民の主張が食い違うことがあるし、交渉がまとまらないときには殺傷事件に発展することもある。また、農耕民の間には貧富の差が存在し、貧しい者の富裕者への嫉妬が牧畜民に対する暴力となって表出することもあるという。一方で、新たな共同関係が形成されたり対立を緩和するための営みもなされている。2008年ごろには、農耕民と牧畜民の間でトウジンビエ団子をつくる契約が結ばれたし、食害が発生した場合には村に定住した牧畜民が交渉の仲介役を務めることで、関係のさらなる悪化を抑止している。大山氏自身も、ハウサの人びとの在来知識を活用しながら紛争を緩和するための実践を試みている。具体的には、都市ゴミを利用して対象地域の緑化を進め、緑化した土地を「村人全員」の家畜肥育に資する土地として用いることで、人びとがkowa(共同)で利用できる空間をつくりだそうとしている。
討論では、村の経済格差はもともとどのように生じたのか、といった質問に加えて、別の生態地域でも都市ゴミを利用した緑化は可能なのか、村人からみた大山氏の立ち位置はどこにあるのか、外部から人が入っていくことで現地の人びとの関係はどのように変化したのか、などといった実践に関する多くの質疑がなされた。
討論
総合討論では、アフリカでは共同体的土地保有が支配的であるために土地の経済的な価値を高める誘因が働かないので、個別的土地所有権制度を導入する必要がある、という基本的な問題規定の段階で、多くの論点が抜け落ちていることが指摘された。たとえば移動性が高い暮らしをしている人びとには、土地の価値を高めようという動機がそもそも強く存在しないはずである。さらに、人口が増加するから農業生産力を高める必要があり、そのためには個別的土地所有権を導入する必要がある…という前提自体を疑う必要があるのではないか、との指摘もなされた。これらの指摘に関連して、土地制度の問題については開発経済学者の主張が政策立案につよい影響力を有しているが、それに対してアフリカ地域研究者はどのような発言をしていくことができるのかを考えていく必要があることが論じられた。また、近年になってアフリカ全土で進行中の大規模な「土地強奪(ランド・グラッビング)」に関して、各国の法整備状況に関する議論がなされ、本来なら国民の所有権を担保すべき国家が外国資本への土地譲渡を主導している現状が確認された。これら以外にも、土地登記とは別に、実態として土地の個人所有化がどれだけ進んでいるのか、植民地時代からの「不正義」をどれだけ考慮にいれた土地問題の解決が可能なのか、といった論点が出された。(佐川徹)
[北東アフリカ・クラスター第1回研究会]「北東アフリカ・クラスターはいかに、アフリカの紛争解決に貢献できるのか」(2012年01月27日開催)
日 時:2012年1月27日(金)
場 所:京都大学稲盛記念館 3階 小会議室I
プログラム
北東アフリカ・クラスターはいかに、アフリカの紛争解決に貢献できるのか
報告
本研究会では、北東アフリカ・クラスターが行う最初の研究会ということもあり、メンバーがこのクラスターで取り組みたいと考えている課題について発表したのち、本クラスターが目指す方向性について議論を行なった。
重田氏は調査地でプロジェクトを行なうにあたって、自分自身が土地紛争を経験するようになったため、土地の境界をめぐる紛争の解決方法に関心があると述べた。次に佐川氏が、エチオピアの南オモ県で行われているダム建設や石油採掘、大規模農場の開発といった大規模な開発プロジェクトが引き起こす紛争について、エチオピア南部の半乾燥地域に暮らすダサネッチに注目しながら検討していくことを述べた。伊藤氏はエチオピアで観察されたジャールサ(jarsa)という紛争解決方法について触れたのち、北東アフリカという枠組みで扱うことができるテーマを模索中であることを述べた。遠藤氏はこれまでソマリランドにおける調停活動に重点をおいて調査を行なってきたが、今後はプントランドにおける和解のプロセスに注目したいと述べた。栗本氏はモニョミジ(Monyomiji)という紛争解決方法に興味がある点を述べ、ローカルな紛争解決のメカニズムには限界があるため、それを仲介する機関や組織の可能性を探りたいと述べた。内藤氏は現代のアフリカにおいて、グローバリゼーションのなかで展開する非西欧的な国家や市民社会の可能性について検討したいと述べた。
その後の議論では、まず北東アフリカ諸国がそれぞれ体験している紛争の背景や種類は大きく異なるため、北東アフリカという枠組みで考えるのは難しいという点が確認された。また、潜在力を疑う必要があるという点、対象としている紛争がどのようなものなのか検討する必要性、近代化ということに対して、「経済発展か文化の維持か」という二項対立的な考えかたを再検討する必要性などについて話し合いが行なわれた。そのほか、都市部の紛争解決方法やマスメディア、宗教や外部アクターの役割、またローカルな活動だけではなく、ディアスポラにも注目する必要性について検討が行なわれた。
最後に次回の研究会は5月12日に、弘前大学の曽我亨氏と京都大学の伊藤義将氏を発表者に迎えて行なうことを決定して研究会を終了した。(伊藤義将)
[南部アフリカ・クラスター第1回研究会](2012年1月27日開催)
日 時: 2012年1月27日(金)
場 所: 京都大学稲盛記念館 3階 301号室
プログラム
問題提起と自己紹介
報告
世話人の峯陽一さんから南アフリカにおける入植の歴史、ヨーロッパ系の住民とバントゥー系住民の重層的な関係、HIV/AIDSの問題などを取り上げながら、この研究会が南部アフリカにおける紛争と共生をどのように扱っていくのか問題提起をおこなった。そののち、各自の研究者(遠藤貢、高田明、丸山淳子、クロス京子、阿部利洋、海野るみ、大山修一)が研究内容と問題意識を紹介した。さいごに峯さんから、①研究課題である紛争とポテンシャルをどう扱っていくのか、②アパルトヘイトを代表とする南アフリカ共和国の陰の部分をどうみるのか、③国家による国民統合とその排除、④アイデンティティのゆらぎ、⑤人々が移動してきたモビリティをどうみるのか、といった5点の総括がおこなわれた。さいごに、来年度の予定について打ち合わせた。(大山修一)
[第1回アフリカの紛争と共生 国際フォーラム(ナイロビ)](2011年12月02-04日開催)
日 時:2011年12月2〜4日
場 所:ナイロビ Silver Springs Hotel
概要
本プロジェクトでは、とくにアフリカ人研究者・実務者をまじえて国際的な議論を深めるために、「アフリカ紛争・共生フォーラム」を毎年アフリカ各地で開催することにしています。2011年度には、その第1回をナイロビで開催しました。
このフォーラムには、アフリカ5カ国(ケニア、エチオピア、南スーダン、ウガンダ、タンザニア)からそれぞれ二人ずつ合計10人を招へいし、日本からは本プロジェクトのメンバー6人が参加しました。参加者には、まえもって以下の三つの質問を送り、それに答えるかたちで2000~3000語のメモを用意してもらって、会議の当日には、それをもとにして議論をしました。
(1)アフリカの紛争解決や和解、社会的な癒しを実現することに貢献することが可能な、アフリカの潜在力とは何か
(2)アフリカの潜在力を活用した紛争解決・和解の試みの萌芽があれば具体的に示してほしい
(3)紛争処理における、普遍的正義を保証するための国際的枠組(たとえばICC)と、アフリカの潜在力を活用した上記の枠組とはどのような関係であることが望ましいか
1. What is African Potentials that can materialize conflict resolution, reconciliation and social healing?
2. Do you know any examples of trial in which African Potentials are utilized in conflict resolution and social healing?
3. In conflict resolution, international frameworks (such as ICC) are often utilized in attempts to secure universal justice. What kind of relations is desirable between African Potentials and such international frameworks? How can they be articulated?
プログラム(各発表の要旨を読むためには、タイトルをクリックしてください。
また、ここをクリックすれば要旨全部をまとめて読むこともできます)
December 2
- 18:00-19:00 Registration at Ostrich Conference Room
- 19:00-21:00 Welcome Dinner at the Hotel
December 3
- 9:00-9:30 Itaru Ohta (Kyoto University)
- 1. African Potentials, Customary Knowledge and Institutions, and Persistent Face-to-face Interactions
- 9:30-9:55 Eisei Kurimoto (Osaka University)
- 2. Limits and Possibilities of “African Potentials” in Conflict Resolution and Co-existence: Towards an Endogenous Approach of Peace- building
- 9:55-10:20 Gebre Yntiso Deko (Addis Ababa University)
- 3. African Peace Potentials: Insights from Ethiopia
- 10:20-10:35 Break
- 10:35-11:00 Kennedy Mkutu (United States International University)
- 4. African Potentials for Conflict Mitigation in and around Kenya
- 11:00-11:25 Fekadu Adugna Tufa (Addis Ababa University)
- 5. Assessing “African Potentials” among the Pastoral Somali and Oromo in Southern Ethiopia
- 11:25-11:50 Mikewa Arunga Ogada (Centre for Human Rights and Policy Studies)
- 6. A Research Note on the Work of Clerics-Led Peace Committees in Kenya’s Coast
- 11:50-12:15 Haji Abdu Katende (Makerere University)
- 7. The Strength of African Conflict Resolution Potentials
- 12:15-13:35 Lunch Break
- 13:35-14:00 Samson Wassara (University of Juba)
- 8. “African Potentials” from South Sudan
- 14:00-14:25 Toshimichi Nemoto (Japan Tanzania Tours Ltd.)
- 9. Peaceful 50 years of Tanzania
- 14:25-14:50 Simwana Said (Tanzania Center for Foreign Relations)
- 10. Tanzania Conflict Management within Great Lakes Region and the Horn of Africa
- 14:50-15:05 Break
- 15:05-15:30 Naoki Naito (The University of Tokushima)
- 11. Coping with the State and Non-state Actors: Lessons from Local Peace Building Practices in Kenya
- 15:30-15:55 Toru Sagawa (Kyoto University)
- 12. Relational Networks and Peace-Making in East African Pastoral Societies (South Omo)
- 15:55-16:20 Simon Monoja Lubang (University of Juba)
- 13. Conflict resolution and potential in African context
- 16:20-16:35 Break
- 16:35-17:00 Edward K. Kirumira (Makerere University)
- 14. Local Communities as Agency in International Conflict Conciliation Frameworks: Re-visiting African Potentials
- 17:00-17:25 Motoji Matsuda (Kyoto University)
- 15. Beyond Romanticization of Customary Mechanism of Conflict Resolutions: Notes for Further Discussion
- 17:25-18:00 General Discussion
December 4
- 9:30-11:30 General Discussion
議論された主要な課題
■本フォーラムの第一日目には、合計15の報告がなされたが、そのなかから以下の共通の問題点が浮き彫りになった。第2日目には、こうした課題についてさらに議論を重ねた。
(1)紛争解決のためには、国家が用意しているメカニズム、制度、枠組み(たとえば裁判所)があるが、それと、在来の・慣習的な・伝統的なメカニズムとは、どのような関係にあるのか(あるべきなのか)
- 双方は、補完的、協力的なものなのか。在来のメカニズムは、国家の枠組みから、どれだけ独立し、自律的なのか。国家によって、公式に、法的な認可を受ける必要があるのか(そもそも、「法の支配」とは何か、「法」とは何か)
- 国家や都市在住のエリートたちは、在来のメカニズムを利用したり、操作したりすることによって、より強力な権力をふるうことはないのか、それは不可避なのか(国際機関やNGOではたらくものたちは、どうか)
- 国家が人びとを保護しないとき(国家が不在のとき)、在来のメカニズムは重要になると考えられるが、それはどのように活用できるのか
(2)在来のメカニズムがはたらくところ(空間)は、どのようなものか
- それは、国家権力が不在であるような周辺地域において、コミュニティのレベルではたらくだけなのか
- 在来のメカニズムは、(国家権力が不在である地域で、その)オルタナティブとして活用されるだけのものなのか、あるいは、たとえば国際紛争の解決のために活用できるような、もっと魅力的なものなのか(そうであれば、どのようにして?)
(3)「アフリカの潜在力」「アフリカの知識」「アフリカの知恵」「アフリカの哲学」「アフリカ的な実践」とは、何か。
- それは、国家によって現実化するものか、より大きな地域によってか、あるいは、より小さなコミュニティや慣習を共有する集団か、あるいは個人によって現実化するものか。
- もし、このように複数のレベルではたらくものであれば、異なるレベル間は、どのように接合することができるのか。
- アフリカの潜在力は、人びとの日常生活にねざしたものと語られるが、常にそうでなければならないのか(政府やNGOの介入による草の根の平和構築プログラムをどう考えるか)
(4)グローバルで普遍的な枠組み・基準・価値とアフリカ的な枠組み・基準・価値
- 在来の慣習には、「よいもの」と「わるいもの」があるのか、誰がそれを判断するのか、在来のメカニズムは人権侵害をおこすのか(特に女性と子どもたちに対して)、「政治的に正しくない」側面をどう考えるか
- グローバルな枠組みでは個人が重視されるが、在来の枠組みでは集団が重視されることをどう考えるか(たとえば相互に争った二集団の和解を考えるとき、近親者を殺された個人の感情を重視するか、集団としての和平を優先するか、個人の不平不満をどうあつかうのか)
(5)伝統、慣習、あるいはジャスティス(正義?)、真実、和平といった概念をどのように定義するのか
- 「伝統的(在来の)権威」「伝統的(在来の)メカニズム」とは、どこまで「伝統的(在来)」なのか(それは、コロニアル、ポストコロニアルに、ねつ造されたものではないのか)(ステレオタイプな伝統観をどうするか)(近現代の変容の問題をどうするのか)
- 修復的正義と応報的正義
- 顕微鏡的な(具体的な証拠をともなう)真実と対話的な(ともなわない)真実
- ポジティブな平和(貧困、抑圧、差別などの構造的暴力がない状態)とネガティブな平和(戦争がない状態)
[生業・環境ユニット第3回研究会](2011年11月26日開催)
日 時:2011年11月26日(土)15:00~17:00
場 所:京都大学 楽友会館 会議室5
プログラム
経緯と趣旨説明 メンバーによる研究紹介と話題提供 今後の方針についての討論
報告
まず、本ユニットの経緯と趣旨について世話人の山越言さん(京都大学)より説明があった。そして、第1回目の研究会「タンザニア農村における対立回避のメカニズム」、第2回の研究会「アフリカ自然保護の潮流:原生自然保護から住民参加型保全、そして新自由主義へ?」の開催について、伊谷樹一さん(京都大学)と山越言さんから参加者に対して説明があった。第1回目では、タンザニアの村落社会において争いの拡大を未然に防ぐ、紛争回避に関する事例を紹介したうえで、社会に内在する紛争回避メカニズムに関する議論がおこなわれた。第2回目では、自然保護をキーワードにして、環境保護を進める国家、国際NGOといった外部社会と地域コミュニティとの接触が契機となって引き起こされるコンフリクトを取り扱った。そののち、各メンバーが研究内容、関心について紹介したのちに、ユニットの方向性を討議した。本ユニットの性格上、紛争や内戦そのものを取り扱うことは難しいが、外部社会の変化に対する各アクターの対処方法、あるいは紛争の拡大を未然に防ぐ村落社会に内在する紛争回避メカニズムと在来性のポテンシャルに焦点をあてていくことが、ひとつの方向性として確認された。重要なキーワードとしては水、土地、植物、動物をめぐるコンフリクト、国家政策や援助計画、気候変動、ダム建設やツーリズムの導入がもたらす村落社会へのインパクトとその住民対応、市場経済や経済格差のなかでの平等性のあり方などが挙げられ、外部社会からのインパクトを考慮に入れつつ、地域社会のミクロな動きに着目していく方針が立てられた。(大山修一)
[政治・国際関係ユニット第2回研究会]遠藤貢「ソマリランドにおける『下からの』秩序実現の取り組み」(2011年11月26日開催)
日 時:2011年11月26日 (土) 15:00~17:00
場 所:京都大学楽友会館
プログラム
15:00-17:00 遠藤貢(東京大学)
ソマリランドにおける「下からの」秩序実現の取り組み
報告
1991年1月26日にソマリアでシアド・バーレ政権が崩壊すると、同年5月18日に同国北西部に位置し旧イギリス領であったソマリランドが、「ソマリランド共和国」として独立宣言をした。ソマリランドは現在にいたるまで、国際社会から「国家」としての承認を得ていないが、混乱が続く南部ソマリア地域に比べて一定の社会的・政治的安定を確保しているとの評価がなされている。発表では、1990年代にソマリランドで国民レベルの「和解」を目的として開催された2つの会合に焦点があてられた。いずれも、地域レベルで小規模な会合を積み重ねるプロセスの中から実現した「国民」レベルの会合である。とくに1993年1~3月のボラマ会議には、「ソマリランド全体の運命を決する会合」という認識の下に、すべてのクランの長老150名が参加した。会合は多数決による決定を形式としては採用していたが、「votingは fightingと同じだ」という考えが出席者に共有され、話し合いをとおした全会一致で決議をするという方針がつらぬかれた。またその際には、通常対立しあっていると思われるクランが相互に交渉し、連携する形で会合が進展した。結果として、「ソマリランド・コミュニティ、安全と平和憲章」と暫定憲法的な色合いをもつ「国民憲章」いう二つの憲章が制定された。会合後には武装解除や職業訓練も進められ、国内に一定の秩序形成が進んだ。この会合は、国際組織からの援助があったものの、資金の大部分はソマリランダーが自主調達する形で開催されたものであり、外部関与をわずかしかともなわない、ローカル主導で実現した会合であった。これが可能になった背景には、ソマリの慣習法や長老会議の伝統、そして問題解決を図る際に交渉や対話を重視するpastoral democracyの存在などを挙げることができる。
討論では、ソマリの慣習法や長老会議と植民地化以降の社会変容との関係について議論がなされた。ソマリランドが地政学的にどのような位置にあり、どの程度の介入が植民地時代になされたのか、それがソマリの社会―政治構造にどのような影響を与えてきたのか、といった議論である。また近代化の過程で、長老制社会では年長者の権威が教育を受けた若者らによって浸食されることが他地域から報告されているが、ソマリランドではそのような事実はないのか、といった点も議論の対象となった。また、1991年以降の和平プロセスでディアスポラが果たした役割についての質問がなされ、どれほどの資金が実際に流入したのか、そのような資金の流れがクラン間のポリティクスにどのような影響を与えたのか、ディアスポラの関与が新たな対立軸をつくりだした側面はないのか、といった指摘がなされた。さらに、今後ソマリランドが国際的に承認される可能性はあるのか、その過程で(若者や女性が不在の)長老会議が主体となった意思決定のあり方を国際社会が「デモクラシー」として認知しうるのか、といった点も論じられた。(佐川徹)
[第3回全体会議]「南アフリカ共和国における真実和解委員会の活動と人びとの和解」(2011年11月26日開催)
日 時:2011年11月26日(金)11:00〜14:30
場 所:学友会館 1階 会議室
プログラム

10:00~10:15 事務連絡
10:15~11:15 阿部利洋(大谷大学)
「南アフリカ真実和解委員会の活動とその後」
11:15~12:15 峯陽一(同志社大学)
「藪の中の正義と親密圏―ある「良心的アフリカーナー」による南アフリカTRCの記録」
12:15~12:40 休憩
12:40~13:20 山本めゆ(京都大学)
「TRCにおける和解と恩赦」
13:20~14:30 討論
報告
阿部利洋「南アフリカ真実和解委員会の活動とその後」
阿部利洋氏は、南アフリカの真実和解委員会(TRC)の活動内容とその特徴、それに対してなされてきた評価や分析について論じた。TRCの活動は、1995年に制定されたTRC法がその法的基盤となったが、法文上では「真実」や「和解」という語が定義されなかった点が特徴的である。ただしTRCは自己の活動の正統性を確保するためにも、公聴会活動では精密な審査や記録をおこなった。たとえば、TRCはその活動の一つに特赦の付与を含めた点がしばしば注目されてきたが、それは「アパルトヘイトが終わったからたがいに赦しあいましょう」といった、ときに一般に理解されているような内容のものではない。特赦が付与されるためには、なされた行為が「政治的暴力」であったことと、なされた供述が「完全な供述」であることという、ふたつの要件が満たされる必要があった。また実際の特赦公聴会では、TRC委員や会場の聴衆との相互作用によって、自己の責任を否定していた加害者が態度を変更したり、謝罪をおこなった事例があったこと、そしてその場面がメディアをとおして広く国民に伝えられたことが、ふつうの裁判と大きく異なる点であった。
TRCに対する国内での反応としては、法廷での証言者の大多数をアフリカ人が占めておりバランスを欠いていた、被害者支援が不十分であった、などの指摘とともに、2001年になされた国内での社会意識調査では、TRCが人種・民族間関係の改善に果たした役割に対して否定的な回答が目立った。また、国内外から「TRCは~(たとえば、アパルトヘイト政府幹部の召喚)が不十分だった」「TRCは~(たとえば、アパルトヘイト時の汚職の調査)も権限に含めるべきだった」「TRCの基本的な方向性や発想が偏向している」といった批判もなされてきた。阿部氏は、TRCをどう評価し位置づけるのかには多様な立場があることを強調しつつ、自身としては、TRCが「何か良くない状態(たとえば人種間の対立関係)が消滅する」という意味での解決をもたらしたというよりも、南アフリカ社会に「武力衝突から(非暴力的な)交渉・取引・競合関係への移行」をもたらす媒体として作用した可能性があること論じた。
(佐川徹)
峯陽一「藪の中の正義と親密圏―ある「良心的アフリカーナー」による南アフリカTRCの記録」
峯陽一氏は、自身がその邦訳書の解説を執筆したTRCから生まれた著作、『カントリー・オブ・マイ・スカル』(現代企画室、2010年)とその著者についての報告をおこなった。TRCは、その規模の大きさと徹底的な証言記録により特徴づけられるとともに、本格的に免責の制度が導入されたこと、レイシズムに関わる責任が議論されアフリカと西洋との歴史的関係が問われたこと、そして理不尽な死が過剰に存在してきた南アフリカの社会を舞台におこなわれたことが、世界的に大きな注目を集めた理由として挙げられる。この著作は、南アフリカ人の一ジャーナリストが、TRCが進行する渦中で書きあげた「現場からの声」であり、研究者によるより「客観的な」研究成果を補う著作として位置づけうる。また、アパルトヘイト時代の加害者と被害者の関係は、白人と黒人の関係に一対一で対応させられる単純なものではなく、解放運動に関与して殺害された白人や警察のスパイとなった黒人の存在などもありこみいっているが、この著作ではそのような関係のあり方が一定の複雑さを保ちながら描かれている。
著者のアンキー・クロッホは、17世紀半ばにその最初の移民が現在の南アフリカへ入植してきた大陸(おもにオランダ)系白人の子孫、アフリカーナーに属している。アパルトヘイト時代、南アフリカで「ふつうに」くらしていた白人の多くは、大規模かつ組織的になされていた黒人への差別や人権侵害を意識しないままに生活を送ることができた。TRCの場で明るみになった途方もない暴力行為を記者として伝える役割を担った著者は、なによりみずからが「加害集団」の一人であったという事実に直面し、つねにその事実に立ち返りながら記述を進めていく。クロッホは、TRCが次第に国民党やANCらの党利党略の対象とされていったことも批判的に記す。それと同時に、TRCの全プロセスを取材し続けた彼女は、新たな「南アフリカ人」コミュニティをつくりあげていくための条件となる、個人がみずからの罪と責任を認めつつ帰属集団のなかで名誉を保ち続けること、つまり「贖罪と名誉の高次元での融合」の可能性を展望しながら著作を閉じる。(佐川徹)
山本めゆ「TRCにおける和解と恩赦」
山本めゆ氏は、真実和解委員会における恩赦の認定プロセスを検討したうえで、過去の暴力をめぐる解釈の対立、「正義」の認定が困難な状況を明らかにした。恩赦委員会は、1960年代から1994年までの政治的目的と結びつき、アパルトヘイト体制下でおこなわれた個人の行為、不作為、違反を対象としており、恩赦の認定には、過去の加害行為について告白することが条件となされた。恩赦の申請数は7,115件であり、うち1,167件に恩赦が付与された。その申請の多くは、服役中の囚人から提出されたものであり、アパルトヘイト政府の指導者や軍高官からの申請は少なかった。恩赦については、ANCメンバーが一括で恩赦を受けたことに対する旧体制側からの批判と、レジスタンスの暴力は免責されるべきなのかというANC知識人からの批判があった。そして、反アパルトヘイト闘争とアパルトヘイトを支えるための闘争を区別することの是非に対するそれぞれの見解を紹介したうえで、マンデラが真実和解委員会の実効性をもたせる発言をおこない、ANCの諜報機関などが恩赦を申請し、ANC内部の批判勢力を抑えたことが説明された。そして、アパルトヘイト体制における暴力を倫理的に区別することはできるのか、そして、対抗するための暴力は犯罪なのか、真実和解委員会における問題点を整理し、「正義」の認定が難しい現代の紛争の特徴を示した。(大山修一)
討論
討論では、まずTRCを、それ自体として完結した制度や営みとして捉えることの問題が二つの観点から指摘された。一つは、TRCの活動は、南アフリカ社会やその歴史の捉え方を転換させる一つの大きな契機となったことは確かだが、それを紛争処理や和解の終結点とみなすことは妥当ではないという指摘である。TRCが「法的な真実」以外にも「複数の真実」を認め、それらも証言や記録の対象とすることで、通常の司法プロセスでは無視されるアパルトヘイトをめぐる多様な意見や解釈を掬い取ったことは事実である。しかし、そこからもこぼれ落ちてしまう多くの声があり、TRC以外にも、そしてTRC以後にもそのような声を拾い出す試みがなされている。
もう一つは、南アフリカで紛争処理がどれだけ効果的になされたのかという問題を、TRCの制度的問題に還元して説明することは適切ではないことが論じられた。なぜなら紛争処理のあり方は、紛争がどのように始まり、展開し、終結したのか、そして終結後にどの勢力が政権に就いたのか、といった点に規定されることになるからである。移行期司法/正義がなしうることの幅は、あくまで当該社会がそれまでたどってきた経路につよく依存して決定される。これに関連して、アフリカのポテンシャルの「活用」を考える際には、その国や地域で起きた紛争のあり方とその後の体制のあり方を個別的に検討することで、どれだけ紛争処理にポテンシャルが活用できるのかを探っていくことができるかもしれない。
アフリカのポテンシャルについては、阿部氏がTRCは「武力衝突から(非暴力的な)交渉・取引・競合関係への移行」をもたらす媒体として作用した、と指摘している部分に、アフリカのポテンシャルをみてとることもできるのではないか、とのコメントがなされた。阿部氏の述べる「交渉・取引・競合」とは、たとえばアフリカで観察される儀礼の実態と似ている。つまり、機能主義的解釈が想定する「儀礼の執行をとおしてコミュニティが一体化する」というように事態が一方向的に進展することは実際にはまれで、儀礼はしばしば失敗する。しかし、人びとは儀礼を根本的に誤りだとみなすのではなく、儀礼を何度もやり直しながら、そのたびごとに交渉し折り合いをつけ「短期の真実」を見出していくことで事態に対処している。そのような交渉による対処可能性の道が残されていることが、ある種の希望を生み出しているのではないか、という指摘である。
その一方で、TRCが「武力衝突から(非暴力的な)交渉・取引・競合関係への移行」をもたらす媒体として作用した側面があることは確かだとしても、TRCが果たして反アパルトヘイト闘争に参加し命を落とした人びとの思いに見合う場となったのか、あるいはその遺族たちの生活の保障に結びつくような均衡の回復へと向かう流れを南アフリカにつくりだすことができたのか、さらには、TRCにはだれが対等なプレーヤーとして参加することができ、だれが参加できなかったのか、そもそもそのような対等性を確保するためのどれだけの努力が払われたのか、という疑問も出された。くわえて、17世紀半ばから続く差別の歴史を裁くためには、TRCはわずか2年半で終わらせるべきものではなく、むしろ現在まで続けられていてもおかしくなかったのではないか、との指摘もなされた。
最後に、前回のケニアの選挙後暴力を主題とした研究会での議論と重なるが、アフリカにおける紛争処理の全体像を考える際に、アパルトヘイトのような大規模な人権侵害行為はITTや国内法廷などの「法による裁き」をとおして、よりローカルな文脈で発生した紛争はアフリカのポテンシャルを活用することをとおして処理していく、というある種の分業体制を想定することに関する意見交換がなされた。(佐川 徹)


[経済・開発ユニット第1回研究会](2011年11月12日開催)
日 時: 2011年11月12日(土)13:00-17:30
場 所: 京都大学稲盛財団記念館3階小会議室1
プログラム
■プロジェクトの説明 太田至(京都大)
■経済・開発ユニットの趣旨説明 世話人 高橋基樹 (神戸大)
■メンバーによる研究紹介(おひとり20分ほど)
■総合討論
■事務連絡と今後の予定
報告
本科研の研究代表者である太田至氏(京都大学)から、プロジェクトの概要と取り扱う課題群のひろがりについて説明がされたのち、各メンバーが研究内容の紹介と本ユニットで取り扱っていく研究課題について報告した。
世話人である高橋基樹氏(神戸大学)より、経済・開発ユニットが扱う課題として、紛争の要因となりうる希少化する資源を分配するプロセスで生じる失敗または、希少資源を維持するプロセスで生じる失敗をマクロとミクロな視点で、ひろく取り扱っていくことが提案された。
西浦昭雄氏(創価大学)の研究テーマ「アフリカの労働争議と調停方法」が、高橋氏によって代理で紹介された。この課題については、①裁判所のようなフォーマルな調停機能を本研究会ではどのように扱うのか、②フォーマルな調停機能を利用するのは大企業であり、この研究では少数のエリート層を扱うことになるのかというコメントが提示された。①に対して、南アフリカの真実和解委員会の事例が挙げられ、法的根拠がある調停機能だからといって研究対象から外すことはないという点が確認された。②に対しては労働争議にはエリートとは言いきれない人々が多数かかわっている点で、少数のエリートに限定していることにはならないという意見が出された。また、労働者が組織化されていることの社会的な意味について掘り下げることも重要であるという意見が出された。
次に高橋氏の研究テーマである「土地制度と民族関係の政治経済学的分析」について議論された。ここでは特に土地登記の役割が注目された。例えば、土地登記が行なわれたとしても、人々はその権利を売買することはなく、事実上利用していない、土地登記を行なっても、引き続き分割相続を行なうという事例が提示された。また、逆に「登記した」という事実が紛争解決のプロセスに持ち込まれた事例も紹介され、登記の意味が多様化している、ジェンダーの視点からは女性でも登記をしたら土地を所有することが認められるという、ポジティブに機能する可能性も確認された。
池野旬氏(京都大学)は開発や発展によって生じた環境の変化や国家の政策の影響が地方にまで及んだ結果生じた紛争の事例を紹介した。具体的には農村部に建築される学校の土地確保の問題や、生活用水をめぐる地方行政と住民の紛争などが挙げられた。学校用地の確保の問題はアフリカ各地で生じており、土地登記の問題に注目することがここでも重要であるという意見が出された。
小川さやか氏(国立民族博物館)は、①東アフリカ諸国の政治経済連携によって生じる古着取引をめぐる競合と、②政治活動がストリートの古着商人(マチンガ)にまで及び、野党の援助などによって設立されたマチンガ組合がストリートで生じた紛争を解決している事例を紹介した。①に対しては中古品が国境を超えて取引されている状況が政治経済連携によって、貧困削減という方向で機能する場合と、逆にこれまで中古品取引を担っていた人々を除外する方向に動き、貧困を招く可能性も高く、注目に値するテーマであることが確認された。②に対しては、インフォーマルな人々がフォーマルな組織を作っていることが興味深いという意見や、ローカルNGOを作ると儲かるという状況が生じており、お金の流れを把握する重要性も指摘された。
伊藤義将氏(京都大学)は、エチオピア南西部の森林域で2003年より始まった森林保護活動によって引き起こされた地域の混乱を紹介した。このテーマに対しては、状況が非常に複雑になっており、行政のどのレベルの主体が調整機能として働く可能性があるのか不明確であるという点、必ずしも行政単位や村単位で意思決定がされていない場合が多く、想定されている意思決定機構を改めて客観視する必要性がある点などが指摘された。
山田肖子氏(名古屋大学)からは、「社会装置としての教育の影響」という視点から紛争を経験した国の社会科教育、市民性教育がどのように教えられているのか、教科書の分析をすすめることが報告された。今後の調査は主に民族ごとに異なる教育の歴史を持つケニアで行い、教師に注目すると、その教え方などには多様性があり実情を捉えることが難しいことから、教科書を作っている人に限定して調査を行なうということが説明された。また、貧困を削減する方策としての技能形成やskill developmentの可能性を探るというテーマも紹介された。しかし、そもそもアフリカ諸国では就業機会が少ないため、職業訓練を行なっても貧困削減にはつながらないという指摘や、徒弟のようなインフォーマル教育は評価できるが、ある一つの民族がその職業を占有し、他民族が排除される事例が紹介されたり、近年ではコンピューターなどインフォーマルな教育だけでは取得できない技術も多く、フォーマルな教育も重要である点が指摘されたりした。
大山修一氏(京都大学)は、ザンビアで現在進行しつつある、外国人投資家や、企業及び、都市に居住するザンビア人による土地取得の状況について報告した。ザンビアの事例では土地の権利を持っており、土地を外部者に取得されることから守らなければならない存在であるチーフが率先して土地を売却している点などが報告された。また、ニジェール南部サヘル地帯の牧畜民と農耕民の間で生じている土地をめぐる競合についても報告を行い、紛争を解決する方策を思考中であることが報告された。
上田元氏(東北大学)は、これまで行なってきた研究のなかでどのような紛争が見られたのかを紹介した。屋外自動車修理工と都市当局との紛争、半乾燥新開村における女性の蔬菜生産をめぐるジェンダー間の紛争、水や森の管理をめぐる紛争、漁民の資源管理をめぐる紛争などが紹介された。資源を課題として扱うが、民族内の紛争、村内の紛争、世帯内の紛争といったミクロな紛争に注目していくことが確認された。
福西隆弘氏(アジア経済研究所)からは、グローバル化は今後、投資と貿易の分野で進んで行くという視点から、外国直接投資とローカル生産者及び、労働者の関係と中古貿易と産業発展の関係に注目していくことを表明した。外国直接投資の懸念事項として、アフリカ諸国では建設産業は外国企業が中心となり、サブコントラクターとして現地企業が利用されている点、小売・流通業ではスーパーマーケットが進入し小農がなかなか入り込めていない点、園芸産業や農業分野においては適地の少ないエチオピアなどが投資の対象となっている点が挙げられた。しかし、調査手法として、統計資料の調査と現地のインタビュー調査を行なうスキームを考える必要性も指摘された。中古品の貿易については、大規模な中古品の供給がある中で産業発展に取り組んだ例はアフリカしかなく、アフリカの経済成長を考えるうえで手がかりを見出せると報告した。しかし、同時に中古品の輸入には現地の生産者の経済活動を阻害する側面もあり、生産者が輸入中古品にどのように関わってくるのかを見る必要性も指摘された。
荒木美奈子氏(お茶の水女子大)は住民主導で建設されたミニ・ハイドロミルや給水施設等を、一定の「公共性」を持った資源と捉え、その利用や管理をめぐる不一致・内紛や合意形成の過程、在来の規範・制度との接合・関係性などを明らかにしていくと述べた。質疑では、荒木氏が想定している協調的地域社会とは何をもって協調的社会と言っているのか、ある程度意思を持って紛争のない社会を目指している地域社会なのかという点が議論された。
さいごに事務局から事務連絡をおこない、メンバー相互の連絡方法と次回の開催予定(1月28日)について話合った。(伊藤義将)